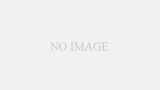カレンダーに「冬至」というに文字が目に飛び込んできますが、
例年12月22日前後は、二十四節気の「冬至」にあたる日なんですね。
北半球では、太陽が出ている時間が一年で最も短くなる日で、
この日を境に少しづつ長くなっていきます。
但し、冬至の日に入りが一年で最も早いと言う訳ではありません。
少しややこしいと思いますが、日の入りが最も早い日は、
冬至の約半月ほど前で、日の出が最も遅い日は冬至の半月ほど後なんですね。
冬至の日は、昼が短い日となっていて翌日から再び日が長く(強まる)なることから、運が向いてくるとも言われています。
ここでは、そんな気になる「冬至」について
・冬至にかぼちゃをたべるのはなぜ?
・冬至にゆず湯の使い方は?
・冬至の時期に食べたい旬の食べ物は?
について分かりやすくまとめましたので、参考にしてください。
冬至とは?
先日「冬至なのでゆず湯にどうぞ」とスタジオの生徒さんから戴いたゆず。しかし生粋の酒飲みである妻は、帰宅するとすぐ黒糖ハチミツゆずサワーを錬成。そして残った皮を湯に浮かべて香りを楽しんでいた。 pic.twitter.com/HSo8AE94nl
— 戌一 いぬいち (@inu1dog1) December 25, 2021
冬至とは、「とうじ」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の一つ(第22節目)
冬至の別名は「一陽来復(いちようらいふく)の日」と呼ばれています。
冬至は、太陽暦の12月22日ごろに始り、
小寒(1月6日ごろ)の前日までの約15日間の期間を指します。
また、一年中で昼が最も短く、夜が最も長い日で、
その日照時間は夏至と比較すると東京で4時間40分程の時間差があります。
緯度が高い北海道ともなると、
日照時間の差は6時間以上にもなります。
古代では、冬至を一年の開始点と考えられていて冬至を太陽が、
生まれ変わる日とし古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われてきました。
日本や中国では、冬至は太陽の力が一番弱まった日ともされ、
この日を境に再び蘇ってくると、考えられており、
冬至を境に運が向いてくる「上昇運に転じる日」ともされています。
また、この日はゆず湯に入ったり、
地方によっては小豆や南瓜(かぼちゃ)を食べる風習があります。
冬至を境に運も上昇するとされているので、かぼちゃを食べて栄養を付け、
身体を温めるゆず湯に入り無病息災を願いながら寒い冬を乗りきる知恵とされています。
「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に冬至の事を、
と記されております。
冬至にかぼちゃをなぜ食べるのはなぜ?

日本では昔から、冬至の日にはカボチャを食べたり、
ゆず湯に入ったりする習慣があります。
カボチャは、7月から8月ごろに収穫の時期を迎える夏野菜です。
また、カボチャは常温で長期保存ができる野菜で、
収穫直後よりも暫く保存しておいた方が、グーンと甘味を増すことで、
秋から冬場にかけて良く食べられるようです。

冬至にカボチャを食べる習慣はいつから
カボチャは南アメリカ大陸が原産なんですね。
生育の温度は25~30℃前後が適温のようです。
また、熱帯性の植物のため、日本ではかぼちゃの旬は夏なんですね。
夏野菜のかぼちゃが、どうして冬の季節になる、
「冬至」に食べられるのでしょうか?
改めて考えてみると「冬至」というのは何だか不思議です。
日本人は季節感をとても大切にしてきました。
春は桜、夏には花火、秋は紅葉、冬はこたつにミカンか冬景色を愉しむというように。
冬至に「夏が旬のかぼちゃ」を食べる風習はどういう理由で、
食べられるようになったのでしょうか。
カボチャには多くのビタミンやβ-カロチンが豊富に含まれていて、
風邪の予防に効果的だったようです。
これは、冬に栄養を摂るための知恵の一つだったんですね。
それにしても、昔の人は凄いですね。
かぼちゃはどれくらい持つの?
かぼちゃは長期保存ができる野菜なんですね。
現代では、ハウス栽培や野菜の冷蔵・冷凍技術が進んでいますが、
昔は、野菜を1年中食べることは困難な時代でした。
そのため、ビタミン類などたくさんの栄養を含むかぼちゃを、
野菜の不足する冬の時期に食べることで、厳しい冬を元気に乗り切ろうという、
江戸時代の人たちの「冬至の日」への想いが込められています。
今は、真冬でもハウス栽培などで、豊富に野菜を食べることができるようになりました。
このように江戸時代から現代まで風習として残っているんですね。
2023-2025年の冬至はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
現在主流の定気法では、
太陽黄経が270度のときで「12月22日ごろ」が冬至です。
また、期間としては、「12月22日ごろ」から、
次の節気の小寒(1月6日ごろ)の前日までを指します。
冬至は、次の二つの期間を意味しています。
■冬至から次の二十四節気「小寒」の前日までの期間
一般的には冬至という場合は、前者の「冬至当日」のこと。
期間としては、12月22日ごろから、
次の節気の冬至(1月6日ごろ)の前日までを指します。
ちなみに、2023年の冬至は?
「12月21日」です。
年代別の冬至は次の通りです。
【2023年】12月21日
【2024年】12月21日
【2025年】12月22日
となっています。
冬至の計算式は次に詳しく説明していますので、参考にしてください。
二十四節気の簡単な算出法
冬至になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2027年までは、次の計算式。
西暦の年を
・4で割って余りが「0以外」の時は、12月22日
となります。
●2028年~2059年までは、次の計算式。
西暦の年を
・4で割った余りが「0か1以外」の時は、12月22日
となります。
冬至にはゆず湯が最適

寒い冬はお風呂でぽかぽかと柚子と一緒につかって温まりたいですよね。
ところで、冬至の日にはなぜゆず湯に入るのでしょうか?
ゆず湯や柚子の活用方法は?
ゆず湯の由来ですが、冬至の読み方は「とうじ」と読むんですよね。
お湯に浸かり、病気を治療する湯治(とうじ)。
冬至=湯治という語呂合わせからきています。
それと、柚子(ゆず)=「融通(ゆうずう)」が効くという願いも込められています。
かぼちゃと違い、一般的には10-12月が旬の柚子は香りも強いので、
邪気を避け、運を呼び込む前の厄払いの目的でも使用するようです。
ゆず湯の効果は
「ゆず湯に入ると、一年間風邪をひかない」と昔からいわれています。
その理由は、柚子には血行促進を行って冷え性を軽くしたり、
身体を温めて風邪を予防する働きがあるそうです。
果皮にはビタミンCやクエン酸が多く含まれていて美肌効果も・・・。
私は冬至以外でもお風呂に入る時、また寒い日にはゆず湯に入っています。
お風呂に柚子の浮かべ方
・柚子を手で揉んで、軽く握り潰しながら湯船に浮かべる。
・柚子を細かく切って、ネットに入れてから浮かべる。
など、お好みによっていろいろあるようです。
敏感肌の方は柚子の搾り汁にヒリヒリとした感覚や、
かゆみなどの反応が出ることがあるので、用心しながらゆず湯を利用しましょう!
冬至のころに食べたい旬の食べ物は?
冬至と言われて真っ先に思い浮かぶのは、
南瓜(かぼちゃ)やゆず湯と言ったところではないでしょうか。
実は、その他にも、冬至の風習の一つに「運盛り」というものがあります。
日本には古来から、季節の節目などにお供え物を飾る(盛る)風習があります。
たとえば、ひな祭りには菱餅、十五夜には月見団子などがその例です。
その風習の一つに、冬至の運盛りがあり、
「冬至の七種」と呼ばれる食べ物をお供えしていました。
・南瓜(なんきん)=かぼちゃ
・蓮根(れんこん)
・人参(にんじん)
・銀杏(ぎんなん)
・金柑(きんかん)
・寒天(かんてん)
・饂飩(うどん)=うどん
これらの食材を見ると共通点が見えませんが、
よく見ると「ん」という文字が2回づつ付く食べ物です。
つまり、「ん=運」のつく食べ物をお供えしていたということですね。
※また「ん」は「いろはにほへと?」の最後の文字なので、
これを食べるとまた初めの文字に戻る(「一陽来復」に通じる)からという意味もあるようです。
その他の風習として、いろいろな風習があります。
語呂合わせの風習では、「冬至=湯治」と
「柚子=融通」をかけて「ゆず湯」に入るというのが有名です。
かぼちゃを食べる風習は全国に残っていて、
現在でも冬至の前には食料品店、スーパーなどで、かぼちゃが売り出されています。

その他、赤い色が邪気払いになるということで、
小豆を使った「小豆粥」や、「赤飯」
さらには砂払いと称して、
一年間で体内に溜まった砂を出すために「こんにゃく)を食べる地域もあります。
とにかく冬はこれからが本番!
栄養のあるものを食べて寒い季節に備えようという習慣なんですね。
まとめ
冬至とは、「とうじ」と読み、二十四節気の第22節目にあたり、
「春分、夏至、秋分」と共に、四季の中央におかれた中気のこと。
冬至は、太陽暦の「12月22日ごろ」にはじまり、
小寒(1月6日ごろ)の前日までの約15日間、またはこの期間の第1日目を指します。
現在の定気法では、太陽黄経が270度のときで「12月22日ごろ」が冬至となります。
冬至の旬の食材は、「ん」のつくものを食べると縁起が良いとされていて、
冬至の七草(とうじのななくさ)と呼ばれるものがあり、
古来から冬至の食べ物として親しまれています。
その中でも、かぼちゃを食べる風習は全国に残っていて、
現在でもゆず湯と一緒に冬至の風物詩として
親しまれています。