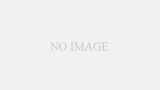大寒(だいかん)とは、一年でいちばん寒さが厳しくなる時期で、冬の最後の二十四節気なんですね。
新しい年が始まって「寒さが厳しくなってきたな~」と感じるころに、「大寒」といわれる季節がやってきます。
この時期は寒さが一段と厳しくなる季節で、空気も乾燥して風邪やインフルエンザに、注意を払う季節でもあります。
この記事では、そんな気になる「大寒」について
・2024年の大寒はいつ?
・大寒の旬の食べ物は?
・2024~2026年は?
についてまとめましたので、ぜひ覚えてくださいね。
ここでは、これらの大寒に関する疑問に、お答えします。
2024年の大寒はいつ?
大寒は二十四節気の一つです。
この大寒の時期を知るために、少しだけ二十四節気について説明しておきましょう。
二十四節気は太陽の動きもとにしています。
太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気というわけです。
これが正確な説明方法なのですが、頭の中に???マークが飛び交っているのではないでしょうか?
事実、節気の求め方は複雑です。誰にでも分かりやすい部分だけを説明します。
365日を24で割ると、一節が約15日ぐらいになりますよね?
この約15日くらいを一節として、それぞれに名前をつけたのが二十四節気なんですね。
季節に合わせた暦なので、毎年同じ季節に同じ節気が巡ってきます。
農業など、季節に合わせて仕事をする人にはとても役立っていました。
さて、肝心の大寒の時期ですが、二十四節気のうち大寒は小寒から数えて24番目の節気となります。
太陽の動きに合わせて節気は変動しますが、
大寒の意味は?

大寒は、1月20日頃から立春(2月3日頃)までの時期を24節気での「大寒」と呼んでいます。
大寒とは、文字の通り1年で最も寒い時期という意味です。
二十四節気というのは、中国で生まれた暦で、日本では、江戸時代から使われ生活に根付いてきました。
大寒は、寒さに耐えしのぐ季節ではありますが、「三寒四温」という言葉があるように、3日間寒い日が続くと4日間は暖かくなり、少しずつ春に向かって季節が移り変わっていく時期と言われています。
また、寒さを吹き飛ばす行事など(寒稽古)などが各地で盛んに行われたり、寒気を利用した日本独自の食文化(高野豆腐、寒天、酒、味噌、など)を仕込む時期にあたります。
「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に大寒の事を
と記されています。
大寒の頃の旬の食べ物とは?
大寒は、二十四節気での第24節目にあたり、立春から数えて最後の節気となります。
大寒を乗り切れば暦の上では、やっと待ちに待った春がやってきます。
大寒は、寒気を利用した食物などを、(高野豆腐、寒天、酒、味噌など)を仕込む時期に適しています。
厳しい寒さのため、空気中の雑菌も少なく、水質も良いので仕込みには最適の環境です。
中でも、味噌や醤油、お酒は発酵させて造るため、雑菌が少ない大寒は最適の時期なんですね。
地方によって寒さの度合いは違いますが、大寒にはしっかりと、防寒対策を心掛けながら、栄養のある食べ物をしっかり摂って、寒さに打ち勝つ身体づくりをしましょう!
旬の食べ物
【野菜】
・小松菜(こまつな)
・水菜(みずな)
・大根
【魚貝類】
・公魚(ワカサギ)【その他】
・鶏卵
・鱈(たら)
大寒卵とは
大寒に食べるといいといわれているのは「大寒卵(だいかんたまご)」です。

寒の内に産まれた卵を「寒卵(かんたまご)」といい、大寒の日に産まれた卵を「大寒卵」といいます。
大寒卵は、子どもが食べると体が丈夫なり、昔から金運や健康運を呼び込むとされています。
現在は品種改良によってニワトリは鶏舎の中で、一年中卵を産む仕組み、が出来上がっていますが、昔は、寒い季節は卵を産まなかったそうです。
そのため、寒い季節に産まれる卵は大変貴重なもので、寒さに負けることなく、産み落とされた卵には滋養があり、強運を持っていると信じられ、縁起物として扱われています。
二十四節気とは?

二十四節気とは、1年を24等分にしています。
そして、季節が移り変わる様を分かりやすくすくするため、それぞれの季節の候に名前を付けた暦のことなんですね。
二十四節気の元は、古代の中国で農業に必要な季節の目安として作られたもので、その後日本へ伝わり平安時代から使われるようになりました。
1年を24等分にすると「365日を等分する」と思いますが、残念ながら、二十四節気は日付というものがありません。
その理由は、太陽と地球の位置関係によって決められているんですね。
太陽は地球の周りを公転し、毎年同じ日の、同じ時間に、同じ位置を通らないんですね。そのため、日付を定めることができないんです。

よく話に出る「春分」「夏至」「秋分」「冬至」の4つはすべて二十四節気です。
この4つの言葉は、「春・夏・秋・冬」の季節の中心と定めた節気のことでで、「二至二分」と呼ばれています。
春・夏・秋・冬には、それぞれ下記の様に節気があります。
季節ごとに、6つの節気があり、計24つになります。
これが、二十四節気の言われるゆえんです。
↓
・春:立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨
・夏:立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑
・秋:立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降
・冬:立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒
また、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」は季節の始まりを示す重要な節気です。
これを「四立」といい、二至二分と合わせて「八節」と呼ばれます。
八節は今でもニュースなどで取り上げられることも多く、馴染みのある言葉だと思います。
それは二十四節気の中でも重要とされている日だからなんですね。
2024~2026の大寒はいつ
■年代別の大寒は次の通りになります。
【2024年】: 1月20日
【2025年】: 1月20日
【2026年】: 1月20日
となっています。
大寒の計算式は次をご覧ください。↓
二十四節気の簡単な算出法
大寒になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2020年までは、次の計算式が有効です。
西暦の年を
・4で割って余りが「0以外」の時は、1月20日
となります。
2023年~2052年までの計算式は
西暦の年を、
なんですね。
まとめ
大寒とは、「だいかん」と読み、二十四節気の第24節目です。
大寒は、太陽暦の「1月20日ごろ」にはじまり、立春(2月4日ごろ)の前日までの約15日間、またはこの期間の第1日目を指します。
現在の定気法では、太陽黄経が300度のときで「1月20日ごろ」が大寒となります。
大寒は寒さが厳しくなるだけではなく年末年始の忙しさで、疲労が出て来る時期でもありますね。
風邪やインフルエンザが一番猛威を振るう時期でもあります。
手洗いうがいなど体調管理に細心の注意を払い、旬の食べ物や大寒卵で体力をつけておきましょう!