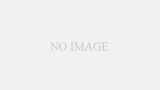六曜とは、カレンダーの日付の下に、「大安」「仏滅」「友引」などと書かれている言葉です。
六曜には、「大安、仏滅、先勝、友引、先負、赤口」の6つの種類があり、
それぞれ意味が異なります。
六曜は、結婚式や葬式など、冠婚葬祭の日取りを決める際に、
誰しも気にするポイントで、特にお年寄りは、真っ先に気にされますよね。
日常生活の中で発生する催事ごとで…
・結婚式に仏滅は絶対ダメ!
・葬式には友引は避ける。
・建築ごとなど祝い事には大安が良い。
など、縁起を担ぐ意味でも六曜は結構重要視されるケースが多いですね。
ここでは、「六曜の種類や意味」や「六曜それどれの読み方」
合せて、縁起が良い順番などについて調べて見ました。
参考にしてください。
六曜の種類と意味とは?
六曜とは、その日の「吉凶や運勢」などを示すものとして信じられている考え方です。
六曜にはその名の通り「6つの種類」があります。
それぞれの意味について以下にまとめてみました。
先勝
「先んずれば即ち勝つ」という意味です。
早ければ良く、万事に急ぐことが良いとされる日です。
午前中は吉、で午後は2時から6時が凶とされています。
用事を済ますなら午前中に済ましましょう!(14時~18時は凶)
友引
「凶事に友を引く」という意味があります。
「友を引く」ということからお葬式は慎む日とされています。
また、「勝負なき日と知るべし」と言われ、もともとは「何をやっても勝負がつかない」
という意味の「共引」が解釈が変わって今のものになりました。
朝晩は吉、そのほかの時間帯は吉とされています。
結婚式の日は、友を引くとして好まれるようです。
先負
先勝の逆で、「先んずれば即ち負ける」という意味です。
勝負事や急用はできるだけ避け、万事控えめが良いとされています。
午前中は凶、午後は吉です。
用事を済ますなら午後にしましょう。
仏滅
「仏も滅亡する」といわれ、六曜の中で一番の凶の日とされています。
全てに凶…
特に婚礼などの祝儀は良くない日とされ避けられることが多いですね!
もともとは「物滅」という字でしたが、
いつの間にか、「仏」の字が当てられるようになりました。
仏教とはまったく関係がないです。
大安
「大いに安し」という意味で、万事に用いて吉とされています。
婚儀などの祝儀には特に良い日とされ、この日を選ぶことが多い日です。
また、新しい事を始めるにはこの日を選んで始めることが多いですね。
赤口
「万事に用いない悪い日」という意味です。
これは陰陽道の考え方を取り入れたもので、
どちらかといえば凶日とされ、祝い事などには大凶とされています。
「赤」という文字から火の元、赤い血などを連想させるので、
これらの取扱には要注意とされる日です。
午前11時ごろから午後1時ごろまで吉、その他の時間帯は凶とされています。
前述したように六曜にはそれぞれに細かく意味があります。
大安や仏滅などはわかりやすく、1日中良かったり悪かったりといった感じですね。
ただ、赤口とかはちょっとわかりにくいような部分もあるので、
赤口の意味を良く理解しておかないと活用しにくいですよね。
六曜の読み方は?
カレンダーを見てみると必ずといっていいほど、六曜を目にしていると思います。
このように、月間の日にちで六曜のどれかが表記されていますよね。
その六曜は、「先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口」からなっており、
これらの6つの事を「六曜」と呼びます。
六曜それそぞれの読み方は…
・先勝:せんしょう・せんかち・さきがち
・友引:ともびき
・先負:せんまけ・さきまけ・せんぶ
・仏滅:ぶつめつ
・大安:だいあん・たいあん
・赤口:せきぐち・しゃっこう・しゃっく・じゃっこう
など、いくつかの読み方があります。
読み方については、どの読み方でも構わないと思いますが、
私たちが日常生活の中でよく使う、「大安」「仏滅」「友引」の
以外の言葉はあまり馴染みがないのではないでしょうか?
大安と仏滅、友引などは、日頃の生活の中で何か催事ごとのたびに、
活用されているので、なんとなくその意味は分かるのでと思います。
六曜で縁起が良い順番は?
一般的に、以下が六曜で縁起が良い順番と言われて」いるんですね。
の順番が良いとされています。
基本的に、カレンダーでの六曜の順番は、
「先勝⇒友引⇒先負⇒仏滅⇒大安⇒赤口」を繰り返しとなっています。
ただし、カレンダーでの六曜の法則として、
旧暦の毎月1日ごとに決められた六曜に変わります。
旧暦の1日で変わった六曜から、上記の六曜の順番のを繰り返しです。
六曜のルーツはどこ?
では、この六曜の考え方は誰が、どこで生み出したのでしょうか!
六曜のルーツは、なんと、ビックリ!!「不明」だそうです・・・!!
六曜は、もともとは中国で考えられたものですが、
中国でもほとんど信じられていなかったようです。
日本に伝来してきたのは鎌倉時代の末期ごろとなっています。
しかし、中国での歴史を遡ってみると、結果的にはこんなこと、誰が言い出したの!?
良くわからないというのが結論みたいですね。
そんなルーツが不明の六曜ですが日本では自然に受け入れられたようで、
江戸時代の幕末ごろには暦に入れるのが普通になりました。
日本の文化風習にピッタリハマったのかもしれませんね。
明治時代に入ると、明治政府は徳川の色を消すために、日本の文化を劣悪と考え、
江戸以前の文化をすべて排除、政府が六曜を暦に入れることを禁止しましたが、
第二次世界大戦が終わると、その禁止令もなくなり六曜の復活と共に
六曜ブームが盛り上がってきます。
六曜は日本の文化、風習に深く溶け込み催事事など重要な事を決める判断材料として、
なくてはならないものとして広まっていきました。
ちなみに、公共機関が作るカレンダーには、六曜は書かれていないとのこと。
民間に広まった息の長いウワサが、いつしか格の高い言い伝えみたいな感じになっていったようです。
⇒三隣亡でやってはいけないことは?意味と由来は?2022年のカレンダーと引っ越し&入籍などの対策を紹介!
まとめ
如何でしたか?六曜の意味と読み方について…
その意味と読み方、そして、順番まで、
それぞれキチンとした流れがあったなんて、知らなかった人も多いのではないでしょうか。
もともとは中国で生まれた六曜ですが、
その正確な由来やルーツにについてはよくわからないことも多いようです。
六曜って仏教と関係があるのではと、そう解釈している人は多いようですが、
こうして興味を持って調べないと、中々正しいことがわからないですよね。
これが迷信だと言って信じていない人も多いですが、
何か催事ごと有る時は、一つの知識として知っておくのが良いのかもしれませんね。