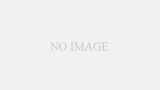カレンダーに表記されている季語で「立冬」とはどういう意味があるのでしょうか?
「立冬」は文字通り冬支度への始まりの言葉ですが、どのような気候を指しているのか?このサイトで詳しく紹介したいと思います。
立冬の「立」とは始まりという意味なんですね。この「立」という意味は「立春」「立夏」「立秋」の言葉にあるように、四季の始まりを表す言葉として使われます。
この記事では、「立冬」について纏めてみました。
・立冬はいつ?
・立冬の時期に食べたい旬の食べ物は?
などについて紹介します。ぜひ覚えてくださいね。
ここでは、これらの立冬に関する疑問に、お答えします。
立冬の意味とは?
今日11月7日は『立冬』です。
暦の上では今日から冬になります。
中国には
「立冬補冬、補嘴空」
といって
「冬になったら冬の食べ物で元気を補おう」
と言う意味の言葉があります。
カボチャ、ほうれん草、ねぎ、白菜、大根、生姜、鯖、鮭、りんご、柿、落花生等が旬なので、温かいお鍋良いですよ! pic.twitter.com/FTgHrsAbWX— CoCo美漢方 田中 友也です。 (@mococo321) November 6, 2021
立冬とは、「りっとう」と読み、冬の始まりを表す日をさします。通常は、この日を境に空気が冷たくなり始めます。また、湿度も一段と低くなって、冬の気配が一段と濃くなり始める季節なんですね。
立冬の「立」とは始まりという意味です。この「立」という言葉は「立春」「立夏」「立秋」にあるように、四季の始まりを表す言葉なんですね。
立冬は、毎年11月7日頃から始まりますが、2023年は11月8日(水)から始まります。また、太陽黄経が225度の日を言います。次の二十四節気「小雪」の前日までが「立冬」になります。
二十四節気が使われていた頃とは、暦がずれている今ですが立冬といっても「冬が来た」と感じる事が少なくなった昨今です。
立冬は、1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の第19節目で、
立春、立夏、立秋を合わせて、四立(しりゅう)と呼ばれ、季節の区切りとして重要視されています。。
また、季節的に「冬の気配を感じる日」で、暦の上ではこの日を境に冬になります。
立冬の時期は、現実的にはまだまだ紅葉が美しい季節ですね。
冬というより秋の印象が強いかもしれません。
と同時に、冬の木枯らしが拭き、北国や高地では初冠雪の便りが届くのも、
この時期でまた時雨の季節でもあるんですね。
また「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に立冬の事を
と記されています。
立冬はいつ?

二十四節気は、冬至を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
現在主流の定気法では、太陽黄経が225度のときで「11月7日ごろ」が立冬です。
また、期間としての意味もあり、その場合は11月7日ごろから、次の節気の小雪(11月23日ごろ)の前日までを指します。
立冬には、次の二つの種類があります。
■立冬から次の二十四節気「小雪」の前日までの期間
一般的には立冬という場合は、前者の「立冬当日」のこと。
期間としては、11月7日ごろから、次の節気の小雪(11月23日ごろ)の前日までを指しています。
ちなみに、2023年の立冬は?
「11月8日」となります。
冬至の算出法は次を参考にしてください。
立冬の体調管理に気をつけよう!
暦の上では、今年も寒い冬がやってきたという事ですが、
季節は秋真っ只中のシーズンですね、周辺に色鮮やかな紅葉が広がる季節です。
立冬の初めは日中と夜の気温差が激しいので、紅葉がどんどん進みますが、
私達にはその気温差が身体に負担になり、インフルや風邪を引きやすい時期でもあるんですね。
なので、出かける時が暖かいと、大丈夫だと思ってつい薄着のままで出かけると、
夜帰る頃に冷え込んできて、薄着したまま出かけたので体が冷えて、風邪を引いたりします。
風邪をひかないようにする為にも暖かい服を用意したり、
疲れて、体に負担がかからないように食べ物で十分な栄養をとることが大切です。
立冬は体を冷やす食べ物に注意
昼間が暑いと身体を冷やす物を摂っていると却って体に負担がかり、
もっと体を冷やすことになります。
「秋なすは嫁に食わすな」
という諺がありますが、「秋なすを食べさせない」という意地悪な解釈になりがちですが、
秋なすは「体を冷やす食べ物なので嫁に食べさせると身体を壊して嫁の身体に負担がかかるからいけないよ!」
という優しい気持ちから生まれた諺なんですね。
昔の人がこのように言っているように、
立冬前後は身体を温める食べ物をとり、健康に気をつけましょう!
立冬の時期に食べたい旬の食べ物は?
明日は「立冬」ですね。
立冬とは「冬の気配を感じる日」で暦の上ではこの日から冬になります。
中国では立冬には「立冬補冬、補嘴空」という言葉があり「冬になったら冬の食べ物で元気を補う」という意味です。
旬の白菜、大根、生姜、鯖、鮭、牡蠣、りんごなどを食べて寒さ厳しい冬に備えましょう! pic.twitter.com/j0lmOvrN4Z— CoCo美漢方 田中 友也です。 (@mococo321) November 7, 2019
立冬には冬瓜(とうがん)を食べよう!
冬瓜は夏に収穫するのが一般的です。
その冬瓜は冬まで保存できるので冬瓜(とうがん)と呼ばれています。
冬瓜は95%が水分で、中に多くのカリウムを含んでいるので、ナトリウムを排出して、
血圧を正常に保つ働きなど、老廃物も排出してくれて、むくみ改善を促進するらしいです。
また、ビタミンCを多く含んでいる為、美肌効果、免疫力を高め感染予防する働きもあるようです。立冬には、冬至には「かぼちゃ」を食べると良いとされているのものは、特にありません。
また、中国には「立冬補冬、補嘴空」(立冬時、栄養を補給)という諺があります。
この言葉は「冬になったら冬の食べ物で元気を補おう」ということなんですね。

冬瓜の食べ方 1
冬瓜の食べ方 2
立冬のころの旬の食べ物>
これらの食材を見れば、やっぱり「鍋物」が定番ですね。
白菜、おねぎ、ニラなどはお鍋の定番です。
また大根と生姜は薬味を入れて食べると美味しいです。
そして魚の鍋としては、
毛蟹、鮭、牡蠣など食材を生かした鍋物は体が温まり元気がでます。
二十四節気の簡単な算出法
大寒になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
立冬になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2031年まで有効なのが、次の計算式。
・4で割った余りが「3以外」の時は、11月7日
が立冬となります。
●2032年~2067年までは、次の計算式。
が立冬となります。
まとめ
立冬(りっとう)と読み、(にじゅうしせっき)の第19節目です。
現在主流の定気法では、太陽黄経が225度のときで「11月7日ごろ」が立冬となっています。
寒い冬がやってくると、寒さでどうしても体が思うように動かなくなるので、
体を小さくして過ごしがちになります。
何もしなければ、体がなまりますし、健康によくありません。
来るべき冬に備えて、体づくりを日々心がけましょう。