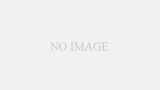「小雪」は二十四節気のひとつで、少量の雪が降る頃という意味です。
この時期になると、山などに雪が降る時期となりますが、
雪が積もるか積もらないか程度の雪を小雪(しょうせつ)と表現しています。
小雪の時期は、時には雪が降り始める(地域によります)ほどの寒さになりますが、
気候的には行事や行楽・イベントなど様々な催しが楽しめる時期でもあるんですね。
ここでは、そんな気になる「小雪」について
・2022年の小雪はいつ?
・小雪の意味は?
・小雪の時期に食べたい旬の食べ物は?
についてまとめましたので、ぜひ覚えてくださいね。
小雪の時期には、11月23日、「勤労感謝の日」がやってきます。
この日は、全国の神社において「新嘗祭(にいなめさい)」として昔から催し物が行われます。
あなたも今年の冬を乗り切るために、新米や旬の食べ物など供え、
感謝して「小雪」を迎えてみてはいかがでしょうか?
ここでは、これらの小雪に関する疑問に、お答えします。
小雪とは?
二十四節気は「小雪(しょうせつ)」を迎えました。
小雪とは、雪が降りはじめるころ。
まだ積もるほど降らないことから、小雪といわれたようです。ただ、山の峰々はうっすらと白くなり、本格的な冬の訪れを感じます。小雪と七十二候、旬のものなどご紹介します♪https://t.co/yrueiZqUnJ
— 暦生活(こよみせいかつ)|10周年 (@543life) November 21, 2022
小雪とは、「しょうせつ」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の第20節目になります。
小雪の期間は、11月22日ごろに始り、大雪(12月7日ごろ)の前日までの約15日間、
またはこの期間の「第1日目」を指します。
北国の地方では、初霜が下りる頃で、
冬とは言えまだまだそれほど積雪は多くないという意味なんですね。
なお、気象庁の予報用語で、
だそうです。
また「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に小雪の事を、
と記されています。
2022年の小雪はいつ?
また、期間としての意味もあり、その場合は11月22日ごろから、
次の節気の大雪(12月6日ごろ)の前日までを指します。
二十四節気は、冬至を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
小雪は、次の二つの期間を表しています。
■小雪から次の二十四節気「大雪」の前日までの期間
一般的には小雪という場合は、前者の「小雪当日」のこと。
期間としては、11月22日ごろから、次の節気の大雪(12月7日ごろ)の前日までを指します。
ちなみに、2022年の小雪は?
年代別の小雪は次の通りになります。
【2020年】11月22日
【2021年】11月22日
【2022年】11月22日
【2023年】11月22日
【2024年】11月22日
小雪の計算方式は次の算出法を参考にしてください。
二十四節気の簡単な算出法
小雪になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2015年まで有効な計算式。
西暦の年を
・4で割って余りが「3以外」の時は、11月22日
が小雪となります。
●2016年~2051年までは、次の計算式。
が小雪となります。
小雪のころに食べたい旬の食べ物は?

小雪は、海の幸、山の幸(野菜)など食材は豊富にありますが、
この日に食べれば縁起が良いとされる食材はありません。
小雪のころの旬の食べ物
【野菜】
・春菊(しゅんぎく)
・長葱(ながねぎ)
・大根(だいこん)
・蓮根(れんこん)
・青梗菜(ちんげんさい)
・小松菜(こまつな)
・カリフラワー
・ブロッコリー
・南瓜(かぼちゃ)
・エリンギ
・長芋(ながいも)
・里芋(さといも)
【魚貝類】
・タラバ蟹
・伊勢海老(いせえび)
・河豚(ふぐ)
・平目(ひらめ)
・ハマチ
・鯖(さば)
・鰆(さわら) など
この季節の
食べ物は、何と言ってもお鍋ですね。
鍋にいれる食材は栄養豊富で身体の芯から温まりますのでオススメです。
その中でも特に白菜は好き嫌いが少なく、お鍋には欠かせない食材です。
まとめ
小雪とは、「しょうせつ」と読み、二十四節気(にじゅうしせっき)の第20節目になります。
定気法では、太陽黄経が240度のときで「11月22日ごろ」が小雪となっています。
また、期間としての意味もあり、その場合は11月22日ごろから、次の節気の大雪(12月7日ごろ)の前日までを指します。
また、北国地方では、初霜が下りる頃で、冬とは言えまだまだそれほど積雪は多くないころです。
小雪には、海の幸、山の幸(野菜)など食材は豊富にありますが、
この日に食べれば縁起が良いとされる食材はありません。
この季節は栄養豊富なお鍋がオススメです♪ 身体が芯から温まりますよ♪