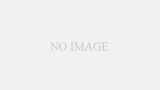年度始めになると「PTA役員」を決める時期が否応なしにやってきますよね。
息子が入った小学校の入学早々に、
PTA役員の選挙があり皆からの投票でPTA役員になってしまいました。
まさかのまさかの出来事にビックリです( ;∀;)
私は学生時代から選挙が嫌で嫌で仕方なかった方なので、PTA役員の選挙なんてとんでもないと思っている人間なんですね。
そんな人間なのに、幼稚園で役員が当たってしまいバタバタした日々を送っていたので、今年はのんびりしたいなと思っていた矢先にまた役員になってしまいました(*’ω’*)
このようにPTA役員になった経験を元に困った事、悩んだ事その他いろいろな事をご案内しています。
あなたがPTA役員に選ばれた時に少しでも、参考になれば嬉しいです。
この記事では、
・小学校のPTA役員のトラブル時の対処法
・小学校のPTA役員の不公平にならない方法は?
などについて分かりやすく解説します。
PTAって何?
PTAとは「Parent-Teacher Association」の略で、教職員と親とが協力する組織なんですね。
この組織は、学校だけではなく地域一丸となり、子どもたちが健康的に過ごし安心して学べるようサポートする組織です。
PTAの仕事は役員により様々です。
PTAの仕事は、バザー・運動会などの運営や、登下校時の子ども見守り、広報活動などその他いろいろあります。
PTA役員の決め方や仕事内容、任期など活動の細かな事は学校によって変わります。
初めて子供が小学校に行く時は、PTAについて分からないことだらけで不安になります。
できることなら上級生のいる家庭に学校での様子を聞いておくことをおすすめします。
それが可能ならいくらか、心の準備ができます。
一般的には、PTAの入る、入らないは任意ですが、現実は子どもの入学と同時に自動的に加入するケースが多く見受けられますが、最近はコロナ禍の影響もあり、PTA活動を見直す学校も増えているようです。
PTA役員の決め方でいい方法は!
小学校のPTA役員を決めるのに驚いたこと。
『必ず一人以上推薦で
誰かの名前とその理由を書き
毎年、提出しなければならない』まぁ、びびったな。
『推薦する人→自分
理由→相手の承諾なしに勝手に
他人の名前を書くことはできないから』で提出した。
この決め方で正しいのか疑問だ。— ピッコロ (@zamamiyababy) January 19, 2021
① PTA役員をくじ引きで決める方法!
圧倒的に多いのはくじ引きで決める方法ですね!
この方法は公平性という面では一番いいと思います。
くじ引きは挙手した残りの人たちだけでくじを引きます。
この方法は公平性としては結構いいと思いますが、問題が一つあります。
それは欠席した人をどうするかです。
前もって欠席することが分かっている場合は知り合いのママ友?にでも、
お願いして「くじを引いて貰う」ことを了承して貰う必要があります。
結構、面倒くさいと思いますが後々の事を考えると仕方ないですね!
また、中にはくじを引いて当選したけどやっぱり「私には無理!」、
と断ってくる人もいることを念頭に入れておく必要があります。
事実、私の時にくじを引いて当たった当選者から、以下のような内容で言い訳の断りが・・・
「高齢者の親の介護が必要なので・・」「父子家庭だから・・・」
と断りが入り困った事になっていました。
※くじ引きは公平な一つの方法です。そしてとても便利な方法です。
でも当たった人の拒否にもちゃんと対応できるように準備しておくことが大事です。
② PTA役員をじゃんけんで決める方法!
これも一般的によく使われる公平性の高い方法です。
じゃんけんは全員が出席しているのであればおススメの方法です。
でも欠席者がいる場合は、くじ引きの場合より面倒になりますね。
また欠席者の代わりにじゃんけんして勝ってしまったら、
代理の人もそうですが、責任を感じかねないですよね。
その他良くする選考方法の一つとして(じゃんけん)
「出席者の中からくじ引きで〇人決める、そして欠席者の中からくじ引きで〇人決める」と、
いった形を取ったりするとより公平さが出ますよ。
③ PTA役員を推薦方式で決める方法!
PTA役員を決める時に推薦方式を地域によっては取っている所もあるようです。
前任の役員さんが、
「この人がこのPTAの役員の役割にピッタリ!」ということを伝えるやり方です。
でも本当はしたくないのにと、断られずに引き受けてしまった。
こういう場合、後々にトラブルを生みだす要素がありますので用心しましょう!
④ PTA役員を挙手制で決める方法!
基本的なやり方として挙手制がありますよね。
PTA役員は学年によっていろいろな催し事がたくさんあります。
コロナ感染拡大で問題になっている卒業式や修学旅行、野外学習など、
保護者も重要視している行事がたくさんあります。
そのため、低学年で比較的仕事内容が少なく、
責任も会長などではなく書記などで逃げようと思っている人もいます。
そういう方のために、「今のうちに」と自分から積極的に役を求める人もいます。
まずは積極的にやりたいという気持ちが強い人がいるのかを確認のため、
最初は挙手制が良いと思います。
⑤ PTA役員を投票制で選ぶ方法!
地域のよっては最初から投票制で行くと決めている所もありますよね。

投票だと公平性が担保されるので一番いいと思っている人も多いですが、
難点は知らない人ばかりの中での投票ですので、誰を選んでいいのか困りますよね。
また、選ぶ人の家庭状況も誰も知っている人がいないので分かりませんよね。
投票で、PTA役員になったんだけど 五十音順の投票用紙なんて配ったら、皆んな上から◯つけるに決まってんじゃん。五十音順早い人不利すぎる。で、五十音順が真ん中以降の人は小学校のPTA免れるらしいよ。中学行ったら今度は五十音順逆からの名簿配られるらしいからまた真ん中ら辺の人免れるやん
— らら (@rara_apollo) April 12, 2021
PTA役員を決める時期は?
PTA役員の決める方法は、「4月の最初の保護者会」で行われます。現役のPTA役員が推薦を考えている場合は、前年度の年末頃から、打診が始まることが多いようです。
小学校によりますが、指定制になっているケースが多く、選ばれるメンバーはすでに決まっているので、前年度の1月~2月頃になると担当委員について希望調査があり、3月ごろに決定するようになっています。
その後、1年生が入学する4月に、各専門委員会の委員長・副委員長などを決めます。
PTA役員の内容一覧
仕事内容は下記の通りたくさんあるので、ここでは仕事内容は省略します。
1.PTA会長
2.PTA副会長
3.書記
4.会計
5.監査
6.学級・学年委員
7.広報委員(情報委員)
8.文化委員
9.校外委員(地区委員・安全委員)
10.ベルマーク委員
11.卒業対策委員
など仕事の種類は、11種類あります。
種類が多く役員になる人は大変ですね。
PTA役員の決め方でトラブルを起こした時どうする?
互いに気持ちよく終わらせたい思っても、トラブルを起こしがちなのがPTA役員の決め方ですね。
ではトラブった時はどうすればいいのでしょう。
一番いいのは揉めないようにすることですが、
それでも揉めてしまった場合の対処法をお伝えしておきますね。
参考にしてくださいね!
① 先生を交えて解決方を探る
大人同士で揉めるのは見苦しい姿を見せることになるので最悪の場合、
先生に間に入ってもらのはどうでしょうか。
先生は毎年PTAの役員決め方を見ていると思うので、
きっと良い知恵を持っていると思いますので一度相談してみましょう!
例えば、
2. 学校側はどこまで役員さんへ仕事の分担をお願いするのか?
といった感じで、仕事内容や、これまでの決め方など参考にできることを先生に話してもらいましょう。
② 役員さん同士で話し合う
基本的に役員の決め方は「文句なし」なので、
そこはスッパリ切ってしまうのも一つの方法です。
ただ、断固やらない!という人もいるかもしれません。
そんな場合は何日も話し合いをして決着をつけましょう。
大人ですからそこは穏便に済ませたいですが、
納得いくまで話し合うことも大切かもしれません。
仕事内容も「10は無理だけど8までならできる」
という風に相手も譲歩できるかもしれません。
PTA役員はとにかく学校に出向いたり行事ごとに駆り出されるので、
忙しい人や子どもを預けられない人には敬遠されがちな仕事です。
そういった場合、どこまで助けられるのかを提示するのも一つの案ですね。
③ 決まらない時に不公平にならないするコツとは?
小学校のPTA役員決めで、席をはずしていたら役員にされてた。土日さえ休めない2月にイベントの手伝いとかできるわけないだろ。といわけで、自分の分は決定をひっくり返したが、戻りの遅かったママさんは欠席裁判が結審している。決め方のプロセスに問題があるよね。
— toku1106 (@toku1106) April 19, 2013
PTAの役員を決めた後で良く出る言葉が「このやりかたは不公平で納得できない!」という不満が噴出する事。
「出席者から選ばれるけど、なぜ欠席者は選ばれないの?」
「どうして専業主婦の人が選ばれず、時間が取れず忙しい人が選ばれるのはおかしい!」
このような不満が出るのは事実です。
なので、最初にどのような役員決め方にするのか?
不公平だと思われないようにするにはどうすればいいのか?
を最初に考えてトラブルのリスクを減らすように心がけましょう!
④ 例年の決め方も理解しているく
過去の役員はどのような方法で決めてきたのか?
地域や学校によってそれぞれの歴史がありますよね。
そのことを説明しながらこちらの学校ではこの方法でやってきている、
ということを学校の歴史として伝えることも大事なことです。
PTAは元々歴史があるので、毎年、行われるPTA役員の流れは大切なことです。
長年の慣習を変える場合は、強い反発と反対意見が出ることを覚悟しておきましょう。
もし難しければ、翌年の役員さんに引き継ぐのも一つの方法ですが・・・
⑤ PTA役員の推薦枠は慎重に
推薦する方法は、前もってこの人を推薦しようと!決めていることが多いですね。
本人が「私でよければ役員になりますのでよろしく!」
という場合ならいいですが、
「あの人専業主婦で暇そうだから役員で頑張ってもらいましょう!」
といった理由は止めた方がいいですね。
こぞってみんなが一人の人を推薦したりすると、
トラブルの元になりますので用心しましょう!
PTA役員決めでトラブルにならないコツも紹介!
PTA役員の決め方は下手をするとトラブルになりがちです。
テレビでも「あるある話」として特集されることが多いですよね。
番組の録画予約のためテレビつけたら、PTA役員決めのトラブル特集やってた。うちの学校は違うけど、記名式の推薦方式、しかも担当役員が誰が推薦したか情報漏らすとか最悪だな。
— 旅ぺん (@tabi_pen) February 13, 2015
でもなるべく穏便に済ませたいもの。
役員の決め方でトラブルにならない方法が見つかったらいいのにね。
① 投票の欠席者をどうするのか決めておく
PTA役員選出の場に欠席する人がいたら、どうするかは前もって決めておきましょう。
欠席者に役員を押し付けは無理がありますので・・。
方法としては、トラブルにならないよう、出欠アンケートに前もって書き込む
2. 欠席者は役員選出で決まったことに同意することとする
と明記しておくといいですね。
② PTA役員に決まった後で文句を言わない
じゃんけんやくじ引き、推薦や投票などあらゆる方法で役員を決めたとして、
どの方法で決まっても、後から文句を言わないことを約束してから決めるといいですね。
何故なら人によっては必ずと言っていいほど、後から文句が出るからです。
内容的には、「このやり方は嫌いあまり公平じゃない!とトラブルになることが多いからです。
選ばれた人は決まったらどうあろうと文句をいいがちです。
事前にそのことを念頭においてその場を切り抜ける手段を考えておきましょう。
③ 役員の内容を把握しておく
後々「この役員の仕事は聞いていない!」というトラブルにならないよう、
前年の仕事内容などはまとめておくといいですね。
役員だけはやりたいくない!と言っている人でも、
その内容分かったら「それだったらできるのでやります」と立候補してくれる人もいるんです。
来年度のPTA役員決め、役員の人がクジ引いて強制的に決まるってマジでひどいー!去年は自分で引けたやーん❗️
もはや神頼みじゃん…— カカロット (@kakapo2hukurou) November 30, 2021
PTA役員はとても忙しいので大変!と言ったイメージを持っている人もいますので、
しっかりと仕事内容を理解してもらってから決めて行くようにするといいですね。
④ 情報を簡単に漏らさない
情報が洩れて良くトラブルになっているケースがあります。
推薦枠などで役員が決まった場合「○○さんがあなたを推薦していた」
「○○さんはAさんを推薦していた」という内容を漏らしてしまって、
「何で私を選んだの!」とトラブルになってしまうことが少なくありません。
役員決めで推薦や投票制を取る場合は、
その中身や内容に関して他言しないように気をつけましょう。
もし漏らし他場合は、今後の人間関係にもしこりを残す可能性がありますので、
他言は絶対してはいけません。
まとめ
PTAって聞けば、何となく揉め事がいつもあるような悪いイメージがありますよね。
決めごとがスムーズに決められて何の問題もなく進むこともありますよね!
それを思ったらPTAがあって良かったと思っている人も多いと思います。
実際にPTA役員をやって周囲を眺めて理解したことですが役員には「学校が味方」という感覚が強いように感じます
バックに権威があるので立場が強くなったかのように錯覚しそれを用いようとします
「PTAに入らない」あるいは「退会する」と主張されることは自分たちの人格否定であると感じているようです https://t.co/cKdjBnDdWV— Albert Rasimus (@metsaihmiset) February 13, 2022
PTA役員の仕事をよく理解して貰い役員の決め方をスムーズに行われるようにすることが大切です。
お互いに頑張りましょう!