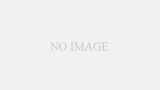カレンダーを眺めていると、時々見慣れない言葉が目に飛び込んできて、
「これって何?」と思うことありませんか。
「清明(せいめい)」も、そんな良く分からない言葉の一つではないでしょうか。
清明は24節気のうちのひとつで春分の次に当たります。
ここでは、そんな気になる「清明」について
・清明とは?
・清明はいつ?
・清明のころの旬の食べ物は?
ここでは、これらの清明に関する疑問に、お答えします。
清明とは?
清明とは、「せいめい」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の第5節目です。
期間は太陽暦の4月5日ごろに始り、穀雨(4月20日ごろ)の前日までの約15日間、
またはこの期間の第1日目を指しています。
清明の名の由来は、「清浄明潔」の略で、
「万物がすがすがしく明るく、生き生きとした様子を表したもの」と言われています。
他にもこの清明は中国から伝わったという説もあり、
琉球(沖縄地方)では清明祭(シーミー)というお墓参りして、
食事する風習も残っていたりします。
清明はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にして、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
清明とは年によって日にちが変わり、
現在多く使われている定気法でいくと、「4月4日ごろ」が清明となります。
また、期間としての意味も含んでいます。
その場合は4月4日ごろから、次の節気の穀雨(4月20日ごろ)の前日までの期間を指します。
ちなみに、2022年以降からの清明は次のようになっています。
↓
・【2022年】4月5日
・【2023年】4月5日
・【2024年】4月4日
・【2025年】4月4日
・【2026年】4月5日
※算出法は下記を参考にしてくださいね。
二十四節気の簡単な計算方法
二十四節気の簡単な計算方法として、西暦の年を4で割った余りが、
「0」の時は、4月4日で、余りが「0」意外の時は4月5日となります。
この算出方法は一定の期限で算出されます。計算方法は2015年までしか有効ではありません。
2016年~2043年までは、西暦の年を4で割った余りが「0と1」とき」は4月4日で、
余りが「2と3」の時が4月5日となります。
清明の時期に食べたい旬の食べ物は?
沖縄地方では、この日を清明祭(シーミー)といって、
内地のお墓参りとは異なり、墓前に親族が集まり、
酒・茶・お重を供えた後、皆でご馳走をいただく習慣があります。
清明祭(シーミー)では、重箱に詰めます。
重箱の中味は、
・「揚げ豆腐」
・「昆布巻き」
・「天ぷら(海老、イカ、魚など)」
・「田芋」
・「皮付き三枚肉(ラフテー)」
・「ごぼう煮」
・「蒲鉾(かまぼこ)」
・「蒟蒻(こんにゃく)」といった縁起の良い食べ物を9品用意します。
<清明のころの旬の食材>
清明のころは川の水も温む季節です。清明の時期に食べてほしい食べ物を以下に挙げてみました。
【野菜】
・新じゃが
・ふき
・にら
・ごぼう
・三つ葉
・タラの芽 など
朝市などへ行くと、鮮度の高い野菜が手にいれることができます。
【魚貝類】
・さわら(鰆)
・初ガツオ(はつがつお)
・さより
・桜海老(さくらえび) など
魚貝類で特にオススメなのが「さよりと鰆」です。
この時期のさよりは特に脂がのっているので、刺身にしたら最高に美味いと言われています。
※ 「清明祭(シーミー)」 について…
沖縄の三大行事の一つ。
中国から伝わったとされ「清明の節」の期間に先祖のお墓に親戚が集まり、
お線香やお花、重箱につめた料理をお供えし供養します。
まとめ
清明とは、「せいめい」と読み、二十四節気(にじゅうしせっき)の第5節目です。
現在主流の定気法では、太陽黄経が15度のときで「4月4日ごろ」が清明です。
また、期間としての意味もあり、その場合は4月4日ごろから、
次の節気の穀雨(4月20日ごろ)の前日までを指します。
沖縄地方では、この日を清明祭(シーミー)といって、
内地のお墓参りとは異なり、墓前に親族が集まり、
酒・茶・お重を供えた後、皆でご馳走をいただく習慣があります。
清明の頃になると、「清く明るい季節」と言われているように、花見や行事も増えてきます。
ぜひ皆さんもいろいろなところに足を運んで、日本の四季を楽しんでみてください。