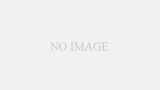カレンダーに表記されている季語で「小寒」という言葉を,
目にする方も多いのではないでしょうか?
「小寒」の頃は、一年の間で最も寒い季節に入り、
寒さが一層深まる意味の事をいいます。
ここでは、そんな気になる「小寒」について
・小寒とは?
・小寒はいつ?
・小寒の時期に食べたい旬の食べ物は?
…についてまとめましたので、ぜひ覚えてくださいね。
ここでは、これらの小寒に関する疑問に、お答えします。
小寒とは?
小寒とは、「しょうかん」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の一つ(第23節目)
小寒は、太陽暦の1月6日ごろに始り、大寒(1月20日ごろ)の前日までの約15日間の期間を指します。
寒さが一段と厳しくなる頃で、
地域によっては大雪の影響で交通がマヒを起こす日が多くなります。
また、この時期はいわゆる「寒の入り」にあたります。
「寒中見舞い」は、小寒の時期から出し始めます。
この日から、寒明け(節分)までの約30日間を、寒の内(かんのうち)といって、
一年で最も寒さの厳しい季節とされています。
なお、寒の入の4日目を寒四郎(かんしろう)、9日目を寒九(かんく)と呼んでいます。
「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に小寒の事を、
と記されています。
小寒はいつ?
二十四節気は、小寒を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
現在主流の定気法では、太陽黄経が285度のときで「1月6日ごろ」が小寒です。
また、期間としては、「1月6日ごろ」から、
次の節気の大寒(1月20日ごろ)の前日までを指します。
小寒は、次の二つの期間を意味しています。
■小寒から次の二十四節気「小寒」の前日までの期間
一般的には小寒という場合は、前者の「小寒当日」のこと。
ちなみに、2023年の小寒は?
「1月6日」です。
年代別の小寒は次の通りになります。
【2020年】1月6日
【2021年】1月5日
【2022年】1月5日
【2023年】1月5日
【2024年】1月6日
【2025年】1月5日
となります。
小寒は次の計算式で出る様になっています。
参考にしてください。
二十四節気の簡単な算出法
小寒になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2024年までは、次の計算式。
西暦の年を
・4で割って余りが「3か0」の時は、1月6日
となります。
●2025年~2056年までは、次の計算式。
西暦の年を
・4で割った余りが「0か1以外」の時は、1月5日
となります。
小寒のころに食べたい旬の食べ物は?
小寒は、年末からお正月にかけてクリスマス、忘年会、新年会など、
いろいろなイベント続きで体に負担がかかり、胃腸が弱りかけている頃です。
年末年始の不摂生や、寒の入りも加わり、
寒さがいっそう身に染みるころでもあります。
こういった時期は、野菜たっぷりのレシピで料理に工夫をして、
体調を整えるように気をつけましょう。
また、1月7日は、「七草粥(ななぐさがゆ)」を食べ、無病息災を願う習慣があります。
ちなみに、春の七草のひとつである芹(せり)が、沢山とれます。
管理人が小さいころは、「芹」は、田舎の道端の小さな溝にたくさん生えていました。
母親の依頼で妹と一緒に良く採りにいっていたのを思い出します。
小寒のころの旬の食べ物
【野菜】
・せり
・なずな
・おぎょう
・はこべら
・ほとけのざ
・すずな
・すずしろ
注:「おぎょう」は、「ごぎょう」とも呼ばれますが、ここでの読み方は、
「ごぎょうは誤り」とする植物学者・牧野富太郎博士の説に依ります。
【魚貝類】
・白子(しらこ)
・鱈子(たらこ) など
七草粥は、年末年始の行事やイベントなどで疲れた胃腸を癒やすには絶好の食べ物です。
他には、大根おろしたっぷりの温かい「おろしうどん」や、
「大根のポトフ」などが胃腸にも優しく、おすすめの食べ物です。
まとめ
小寒とは、「しょうかん」と読み、二十四節気の第23節目です。
小寒は、太陽暦の「1月6日ごろ」にはじまり、
大寒(1月20日ごろ)の前日までの約15日間、またはこの期間の第1日目を指します。
現在の定気法では、太陽黄経が285度のときで「1月6日ごろ」が小寒となります。
1月7日は、「七草粥(ななぐさがゆ)」を食べ、無病息災を願う習慣があります。
年末年始の行事やイベントなどで疲れた胃腸を癒やすオススメの食べ物です。
他には、大根おろしたっぷりの温かい「おろしうどん」や、
「大根のポトフ」などが胃腸にも優しく、おすすめの食べ物です。