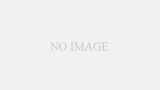カレンダーを眺めていると、時々見慣れない漢字が目に飛び込んできて、
「これって何?」と思うことありませんか。
実際、カレンダーに書かれている『春分』はいつなのか?
そして春分とはどのような意味があるのでしょうか?
ここでは、そんな気になる「春分」について
・春分とは?
・春分の旬の食べ物は?
などの疑問についてお話していきます。
春分はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にして、1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
春分とは年によって日にちが変わり、現在多く使われている定気法でいくと、3月21日頃が春分となります。
また、期間としての意味も含んでいます。
その場合は3月21日ごろから、次の節気の清明(4月5日ごろ)の前日までの期間を指します。
ちなみに、2022年以降からの春分は次のようになっています。
↓
・【2022年】3月20日
・【2023年】3月20日
・【2024年】3月21日
・【2025年】3月21日
・【2026年】3月21日
※算出法は下記を参考にしてくださいね。
二十四節気の簡単な計算方法
二十四節気の簡単な計算方法として、西暦の年を4で割った余りが,
「0と1」の時は、3月20日で、余りが「2と3」の時は3月21日となります。
この算出方法は一定の期限があり、
この計算方法は2023年までしか有効ではありません。
2024年~2055年までは、西暦の年を4で割った余りが「3のとき」は3月21日で、
余りが「3以外」の時が3月20日となります。
春分とは?
春分とは「しゅんぶん」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の第4節目です。
期間は太陽暦の3月21日ごろに始り、清明(4月5日ごろ)の前日までの約15日間、
またはこの期間の第1日目を指しています。
春分には、太陽は真東から出て真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになります。
以後は夏至(6月22日)まで昼が次第に長くなります。
暦では春分の日(3月21日)を中日とし、前後3日ずつ合計7日間を 「彼岸(春のお彼岸)」といい、ご先祖さまの墓参りをしたり、農事始めをする時期にあたります。
この時期は、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってきます。
昔から、「寒さ、暑さも彼岸まで…」と言われてきたように春分を境に気候に変化が現れてきます。
また、春雷がひときわ大きくなりやすい時季でもあります。
春分の時期に食べたい旬の食べ物は?
春分の日には「ぼた餅」を食べる風習があります。
「ぼた餅」を「おはぎ」と勘違いしている方も多いですが、
実は「ぼた餅」が正解なんです。
漢字で書くと…
・「ぼた餅」は「牡丹餅」
・「おはぎ」は「御萩」
となります。
牡丹の花は春に咲くので春分。
萩は中秋の名月のお供え物なので秋分と覚えましょう!
そもそも、萩の漢字には「秋」が入ってますね(*´∀`)
ちなみに、「ぼた餅」と「おはぎ」の違いは、
・こしあんを使ったものが「ぼたもち」で、
・つぶあんを使ったものが「おはぎ」という俗説もあります。
春分のころ旬の食材
春分は春本番を感じる時期ですが,
春分の時期に食べてほしい食べ物を以下に挙げてみました。
【野菜】
・ふき
・アスパラガス など
【魚貝類】
・鯛(たい
・桜海老(さくらえび)
・帆立(ほたて)など
まとめ
春分とは、「しゅんぶん」と読み、二十四節気(にじゅうしせっき)の第4節目です。
現在主流の定気法では、太陽黄経が0度のときで「3月21日ごろ」が春分です。
また、期間としての意味もあり、その場合は3月21日ごろから、
次の節気の清明(4月5日ごろ)の前日までを指します。
春分の日には「ぼた餅」を仏様にお供えしたり、家族揃って食べる風習が根付いています。
「おはぎ」と勘違いしている方も多いですが、「ぼた餅」が正解です。
私の小さい時に母親が作ってくれたぼた餅は、もち米にきな粉をまぶしたもので
中には何も入っていないシンプルなおはぎでした。でも母親が作ってくれるおはぎは最高の味でした。
そのせいか、今でも仏様にお供え後は「ぼた餅」を頂いています。