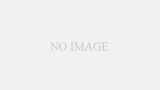カレンダーを眺めていると、時々見慣れない言葉が目に飛び込んできて、
「これって何?」と思うことありませんか。
「穀雨(こくう)」も、そんな良く分からない言葉の一つではないでしょうか。
ここでは、そんな気になる「穀雨」について
・穀雨とは?
・穀雨はいつ?
・穀雨の時期に食べたい旬の食べ物は?
ここでは、これらの穀雨に関する疑問に、お答えします。
穀雨とは?
穀雨とは、「こくう」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気(にじゅうしせっき)の第6節目になります。
期間は太陽暦の4月20日ごろに始り、
立夏(5月6日ごろ)の前日までの約15日間なっています。
また、この期間の第1日目を指しています。
穀雨の名の由来は、
「春雨が百穀を潤す」ということから名づけられました。
雨で潤った田畑は種まきの絶好の時期を迎えるという意味で、
この時期に種蒔きをすると、植物の成長に必要な雨に恵まれるとされています。
この時期の雨が大地を潤すと言われていることから「百穀春雨」と言われたりもします
穀雨はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
現在多く使われている定気法でいくと、
太陽黄経が30度のときで「4月20日ごろ」が穀雨となります。
また、期間としての意味もあり、その場合は4月20日ごろから、次の節気の立夏(5月6日ごろ)の前日までの期間を指します。
ちなみに、2022年以降からの穀雨は次のようになっています。
【2022年】4月20日
【2023年】4月20日
【2024年】4月19日
【2025年】4月20日
【2026年】4月20日
※算出法は下記を参考にしてくださいね。
二十四節気の簡単な計算方法
二十四節気の簡単な計算方法として、
西暦の年を4で割った余りで日にちを判断しますが、
2019年までは殆ど変わることなく、4月20日でが穀雨となります。
2020年~2051年までは、西暦の年を4で割った余りが「0」のときは「4月19日」で、
余りが「0」意外の時は4月20日となります。
穀雨の時期に食べたい旬の食べ物は?
オススメは「新茶」です。
穀雨の末候は八十八夜の時期でもあり、八十八夜に摘み取られる新茶は、
不老長寿の縁起物として古来より珍重されています。
ただ縁起物というだけでなくその年の穀物などの出来高を占う意味合いもあるので、
農耕をされる方は縁起を担いで新茶を呑むのが恒例になっているんですね。
次にオススメなのが、
旬の「よもぎ」です。
食べる機会が少ない人の方が多いと思いますが、
穀雨に食べる食材としては鉄板の食べ物です。
このよもぎは穀雨の時期が旬と言われていますが、
実は「ハーブの女王」と呼ばれるほどの薬草でもあるんです。
春から夏に移る節目の日で、この日から夏の準備を始めます。
<穀雨のころの旬の食べ物>
【野菜】
・よもぎ
・枇杷(びわ)
【魚貝類】
・ホタルイカ
・イトヨリ
・サザエ
・鯵(あじ)
【その他】
・新茶
まとめ
穀雨とは、「こくう」と読み、二十四節気(にじゅうしせっき)の第6節目です。
現在主流の定気法では、太陽黄経が30度のときで「4月20日ごろ」が穀雨です。
また、期間としての意味もあり、
その場合は4月20日ごろから、次の節気の立夏(5月6日ごろ)の前日までを指します。
穀雨の末候は八十八夜の時期でもあり、八十八夜に摘み取られる新茶は、
不老長寿の縁起物として古来より珍重されています。
ぜひ皆さんもいろいろなところに足を運んで、日本の四季を楽しんでみてください。