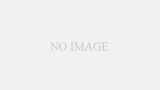カレンダーを見てみると、暦の上で季節を表す,
いろいろな「季語」を見かけることがありますよね。
季語のメジャー用語としては、「春分・夏至・秋分・冬至」などがありますが、
暦の上ではそれ以外のあまり馴染みのない季語が使われていたりしますが、
「霜降」もその一つではないでしょうか?
ここでは、そんな気になる「霜降」について、
・霜降はいつ?
・霜降の時期に食べたい旬の食べ物は?
についてまとめましたので、ぜひ覚えてくださいね。
ここでは、これらの霜降に関する疑問に、お答えします。
霜降はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にしており、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
現在主流の定気法では、
太陽黄経が210度のときで「10月23日ごろ」が霜降です。
また、期間としての意味もあり、その場合は10月23日ごろから、
次の節気の立冬(11月7日ごろ)の前日までの期間を指します。
まとめますと、霜降は、、
2. 霜降から次の二十四節気「立冬」の前日までの期間
の2つの意味があります。
一般的には霜降という場合は、前者の「霜降当日」のこと。
期間としては、10月23日ごろから、
次の節気の立冬(11月7日ごろ)の前日までを指します。
ちなみに、2023年の霜降は?
「10月24日」となります。
年代別の霜降は次の通りになります。
【2020年】10月23日
【2021年】10月23日
【2022年】10月23日
【2023年】10月23日
【2024年】10月24日
【2025年】10月23日
なります。
算出法に関しては下記を参考にしてください。
二十四節気の簡単な算出法
霜降になるの日は、簡単な計算で算出することができます。
その方法は、西暦の年を4で割る方法です。
●2027年まで有効な計算式。
・4で割った余りが「3」の時は、10月24日
・4で割った余りが「3以外」の時は、10月23日
が霜降となります。
●2028年~2063年までの計算式。
が霜降りとなります。
霜降とは?
一般的には霜降と書いて「しもふり」とも読みますが、
二十四節気の霜降は「そうこう」と読みます。
霜降とは、「そうこう」と読み、1年間を24に分けたときの,
二十四節気(にじゅうしせっき)の第18節目になります。
二十四節気で有名なものに、
「春分・夏至・秋分・冬至」などがあり、霜降はその中の一つです。
霜降は、太陽暦の10月23日ごろに始り、立冬(11月7日ごろ)の前日までの約15日間、またはこの期間の第1日目を指します。
気候的には、朝夕の気温が下がり、霜が降りはじめる頃という意味です。
霜降までくると10月後半に差し掛かるので
年末まであと少しと言ったところです。
この日から立冬までの間に吹く寒い北風を『木枯らし』と呼びます。
ニュースなどでは「今日は木枯らし一号が吹きました」と取り上げたりするのもこの季節ですね。
また「暦便覧」という江戸時代に書かれた、季節に関する書物の中に霜降の事を
と記されています。
霜降のころに食べたい旬の食べ物は?
霜降の時期は「さつまいも」が美味しい時期です。
さつまいもは霜降の時期に食べたほうが良いと言われています。
さつまいもの旬の時期ということもありますが、
霜降の頃は肌寒いので、さつまいもを焼き芋にして
食べると、体の芯から温まります。
また、サツマイモは食物繊維が多いので腸内環境を整えてくれる,
食材で知られていますが、栄養価自体も高いのでオススメです。
<霜降のころの旬の食べ物>
【野菜】
・さつまいも
【魚貝類】
・ホッケ
・キンキ(キチジ)
種子島産の安納芋(あんのういも)は、蜜がたっぷりの天然スイーツということもあり
スーパーの店頭でも売られています。 種類が多いので買う時に悩みます( ;∀;)
まとめ
霜降とは、「そうこう」と読み、
二十四節気(にじゅうしせっき)の第18節目です。
現在主流の定気法では、
太陽黄経が210度のときで「10月23日ごろ」が霜降となっています。
霜降の期間は、10月23日ごろから、
次の節気の立冬(11月7日ごろ)の前日までを指します。
この季節はサツマイモが美味しい季節です。少し高価ですが、
種子島産の安納芋(あんのういも)を試しに食べてみては いかがですか?
さつまいもはダイエットに効果があるとのこと、試す価値がありそうです…。