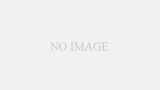カレンダーを眺めていると、時々見慣れない漢字が目に飛び込んできて、
「これって何?」と思うことありませんか。
「啓蟄(けいちつ)」も、そんな良く分からない言葉の一つではないでしょうか
実際、カレンダーに書かれている『啓蟄』には、どのような意味があるのでしょうか?
ここでは、そんな気になる「啓蟄」について
・啓蟄とは?
・啓蟄はいつ?
・啓蟄の旬の食べ物は?
ここでは、これらの啓蟄に関する疑問に、お答えします。
啓蟄とは?
啓蟄とは「けいちつ」と読み、
1年間を24に分けたときの二十四節気の第3節目です。
期間は太陽暦の3月6日ごろに始り、春分の(3月21日ごろ)の、
前日までの約15日間、またはこの期間の第1日目を指しています。
啓蟄とは、啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、
大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃のことをいいますが、
実際に虫が活動し始めるのはもう少し先になります。
主要な公園では、菰(こも)はずし を啓蟄の恒例行事にしているところが多いですね。
マツカレハなどの害虫から守るために、松の幹に藁(わら)でできた菰(こも)を巻きつけること。 春になって、菰をはずすことを「菰はずし」と呼ばれています。
この時期は、一雨ごとに気温が上がり、日差しも徐々に暖かくなってきます。
また、春雷がひときわ大きくなりやすい時季でもあります。
啓蟄はいつ?
二十四節気は、冬至を計算の起点にして、
1太陽年を24等分した約15日ごとに設けられています。
啓蟄とは年によって日にちが変わり、
現在多く使われている定気法でいくと、3月6日頃が啓蟄となります。
また、期間としての意味も含んでいます。
その場合は3月6日ごろから、
次の節気の春分(3月21日ごろ)の前日までの期間を指します。
ちなみに、2022年以降からの啓蟄は次のようになっています。
↓
【2022年】3月5日
【2023年】3月6日
【2024年】3月5日
【2025年】3月5日
【2026年】3月5日
※算出法は下記を参考にしてください。
二十四節気の簡単な計算方法
二十四節気の簡単な計算方法として、
西暦の年を4で割った余りが「0と1」の時は、3月5日で、
余りが「2と3」の時は3月6日となります。
この算出方法は一定の期限があり、
この計算方法は2019年までしか使う事はできません。
2020年~2051年までは、西暦の年を4で割った余りが「3のとき」は3月6日で、
余りが「3以外」の時が3月5日となります。
啓蟄の時期に食べたい旬の食べ物は?
啓蟄に土の中から顔を出してくるのは虫だけではありません。
山菜たちも大地の栄養をたくさん蓄えて顔を出してきます。
その中でもぜひ食べて頂きたい食材があります。
それは「筍(たけのこ)」です。
筍は(たけのこ)は栄養が豊富で、
グルタミン酸やアスパラギン酸などによる、疲労回復効果が期待できます。
食べ方としては、茹でたり、天ぷらにして塩で食べても美味しく頂けます。
<啓蟄のころの旬の食材>
啓蟄は春本番を表す日ですが、
啓蟄の時期に食べてほしい食べ物を以下に挙げてみました。
【野菜】
・筍(たけのこ)
・蕨(わらび)
・新玉葱(しんたまねぎ)
【魚貝類】
・鰆(さわら)
・さより
・青柳(あおやぎ)など
一般的に筍を食べるのは、
5月前後と思っている方が多いのではないでしょうか。
私の経験でもやはり4-5月に筍掘りにいったり、食べたリしていました。
筍の産地が近くにあったということもあり、
シーズンになると結構賑わっていたのを覚えています。
それだけに、筍と聞けば春の到来を感じます。
おススメ料理は何と言っても「筍(たけのこ)と蕨(わらび)の白和え」ですね。
是非一度ご賞味をおススメします。
まとめ
啓蟄とは、「けいちつ」と読み、二十四節気(にじゅうしせっき)の第3節目です。
現在主流の定気法では、太陽黄経が345度のときで「3月6日ごろ」が啓蟄です。
また、期間としての意味もあり、その場合は3月6日ごろから、
次の節気の春分(3月21日ごろ)の前日までを指します。
啓蟄とは、啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、
大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、
穴から出てくる頃のことをいいますが、山菜も大地の栄養をたくさん蓄えて顔を出します。
特に山の幸としては筍(たけのこ)がオススメ!、
筍(たけのこ)は栄養が豊富で、
グルタミン酸やアスパラギン酸などによる、疲労回復効果が期待できます