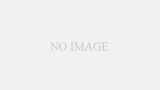あなたは、門松の竹って何故斜めに切ってあるのかご存じですか?しかし斜め切りって本当に不思議な切り方をしていますよね。
まるで居合抜きの刀で切ったようにスパッと綺麗に切れていますものね。
当たり前のように玄関入り口に飾っている門松ですがでもよく見ると、飾ってある竹には「斜めの切り口」や「真っ直ぐな切り口」があるように、竹の切り方にも2種類あります。
その2種類とは斜めに切る「そぎ」と平に切る「寸胴」といわれる切り方があります。
例えば魚の料理でもそうですが、魚や野菜を切るとき、薄くスライスするように切るのを「そぎ切り」といいます。
「そぎ切り」は刃を少し寝かせて上から下に切ります。
もう一つの「寸胴」はスパゲティなどをゆでるとき使われる、口が丸く深い鍋を寸胴鍋といいます。
これは竹の切り口にとても良く似ていて、こちらは刃を水平にして真横に切ります。
この記事では、
・門松の竹の切り口の種類とその理由
・門松の竹の門松の由来や意味と飾る期間は?
などについてお伝えします。
門松の竹の切り口はなぜ斜めに切ってあるの?
一般的によく見かける斜めに切ってある「そぎ」という切り方で、『徳川家康』が始めたものとされています。
「門松の竹の切り口・そぎの切り方とその由来は?
ウィキペディアで「俗説」として紹介されている話の内容です。
↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E6%9D%BE
三方ケ原の戦いで敗走した徳川家康に対し、新年に武田方から句を送ってきたそうです。
「松枯れて 竹類なき あした哉」
松は=松平(徳川)で、竹は=武田を意味します。この意味は、徳川をあざ笑い、武田を持ち上げる内容の歌なんですね。
これに憤慨した徳川方は家臣が機転を利かせ、自軍にとって都合が良いように句の解釈を変えたといわれています。
前述の歌を平仮名で表すと、「まつかれて たけたぐひなき あしたかな」になります。
こうして漢字や濁点を変えた句を武田方に送り返します。
『松枯れで 武田首なき 明日かな』
意味は、「松平は枯れないで、武田は首がないよ」今回は負けたけれど次はこっちが斬ってやるから、と松平家ではこう詠みながら門松の竹の上部を斜めに切り落としたといいます。
これに由来し、門松に使われている「竹の先(首)」を落とした物が槍のように尖らせた物だそうです。
一方、竹を節の部分から水平に切るのは「武田家」の影響下にある土地(山梨等)や、外様大名が支配した土地だとか。
これを境に、松平家の「門松の竹の切り口は斜め切り」となり、徳川家康が江戸開幕後、関東ではこの型の門松が定着したといわれています。
この背景には三方ヶ原の戦いで、武田信玄に敗れたことが原因で家康は信玄と仲が悪くなり、いつか信玄を斬ってやるという意味が込められて作られたそうです。
商売人は違う考え方をしていた?
正月には竹をなんと弾除けとして門松にしたのだそうです。
弾除けとはずいぶん物騒ですが、実際には竹の切り口は斜めに切ると、その切り口が笑口に似ているところから、「笑門来福」(笑う門には福来る)といわれています。
商売繁盛に縁起のよいものとして正月の門松として、切り口が斜めに切り落とされたものが使われるようになったと言われています。
門松の切り口で寸胴ってどういう切り方?
『 門松 』
手作りなので拙い門松で申し訳ないのですが、気持ちを込めて
昔ながらの寸胴の切り口の竹で正月飾りは、末広がりの8がつく本日が良しとされています#水無月 #wine #winebar #bar #抹茶 #macha #cafe #kobe #神戸 #三宮 #生田神社 の近く #alsace #rieslinglover #flower #正月飾り pic.twitter.com/xEUciF5BJT
— 水無月 (@minazuki0006) December 28, 2018
寸胴は武士が好んで使ったと伝えらえています。
その名の通り、切り口は水平で真横に切られています。中にお金が貯まりやすく、貯蓄の意味で金融機関などによく飾られています。
お金が貯まりやすいということでこれは後に一般家庭にも普及し、筒だけて作る慣例となったようです。
昔に比べて家が小さくなったことや、マンションなどが増えたこともあり、竹もカットして小さめのサイズになってきましたね。
門松の貯金箱なんてあったら結構受けるんじゃないでしょうか。
門松を飾るようになった理由は?
玄関の前に飾られる門松で、別名「松飾り」「飾り松」「立て松」ともいいます。
門松を置く理由は、毎年お正月に幸運をもたらす「年神様(としがみさま)」がやってくるときの目印、年神様が宿る「依り代(よりしろ)」としてという2つの意味があります。
年神様とは、1年の幸せを家にもたらしてくれるために山から降りてくると考えられている、神道における新年の神様のことですね。
神様が宿るもののことを「依り代」といいますが、年神様が新しい年に地上に舞い降りてくるときに、落ち着ける宿(家)なのか見つける場所を用意しておく意味で、玄関に門松をおくようになりました。
『松』を使う理由は、常緑樹である松に「祀る(まつる)」や神様を「待つ」という意味をかけています。
正月に長寿の象徴である松を野山から持って帰る、平安貴族の「小松引き」という行事から転じてという理由からです。
門松の飾り方には2種類ある?
門松には飾り方があって、迎え入れたい時には中くらいの長さの竹が内側になるように飾るのよってばっちゃが言ってた。
つまり逆のこれ(出飾り)は推しを修行に出したい本丸向けであって、期間限定鍛刀爆死ダメゼッタイ本丸には向かない。 pic.twitter.com/39uyz6UAfk
— sabisaba/錆鯖 (@sabisa_ba) January 2, 2021
門松の飾り方には2種類あります。
「出飾りと迎え飾」りと呼ばれるものになります。
出飾りとは、一般家庭向きで、竹が1本外に向いているものを出飾りといいます。
外側に向けて結果が出るようにという意味や願いが込められているのです。
迎え飾りとは、商売繁盛や福を家に招くという意味で、商売をしている家に飾られることが多いのです。
門松の意味や由来は

お正月に門松を立てる理由は、ご存じのように門松は玄関の外に立てられるようになっています。
たてる形としては、一対というのが基本です。
3本の竹に松、梅をあしらい、荒縄で結んだものが一般的です。
松竹梅という縁起のよいものを使い、その年の神様を招き入れるためのものとして、
古くから門口に立てられてきました。
神様にずっといて頂き、家が栄え、守られることを願って門松が立てられて来ました。
門松はなぜ3本でそれぞれ長さが違うのでしょうか。
松の長さは7:5:3の割合といわれています。(七五三)
裾に巻く荒縄の巻きも、下7回、中5回、上3回といわれています。
(これも七五三)
2で割り切れない、夫婦仲にも関係あるのかもしれません。
真ん中の竹が仲人(今はあまり縁がないかもしれませんが)で、仲を取り持つという縁起のよいものとして、竹が3本の理由と言われています。
末広がりになっていて富士山を連想させ、縁起のよいものとしては最適なので、大小にかかわらず、今でも人気の縁起物といえると思います。
門松を飾る期間は?

暮れの13日から大安の日が良いとされています。
絶対に避けたいのが29日と31日です。どうしても年末にという場合は28日か30日が良いとされています。
29日は9のつく日は縁起が悪いのと、29は二重に苦しみが来るという意味で避けたほうがよいとされています。
また31日は一夜飾りといわれ、葬式と同じく縁起が悪いとされています。
飾る期間は、正月7日までが一般的です。地方によっては15日のどんど焼きまでというところもあるようです。
終わった後は神社に持っていきます。私のところでは、そうした場所が用意され、自治会などの人がまとめて神社に持って行ってくれます。
忙しくて自分で持っていけない人にとっては助かります。
門松の飾る由来は?
平安時代、すでにお正月に松を用いた行事が残っており、そこから現在のように玄関先に飾るようになったのは室町時代になってからだそうです。
平安時代の習慣の名残で、地域、場所によっては今でも、私たちがよく見かける飾りのついた門松ではなく松の小枝を飾る習慣のところもあります。
まとめ
今回はお正月の門松の切り方には2種類、由来や意味などについてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。
お正月の慣習は、地方によってずいぶん違います。
お雑煮一つとっても、丸餅、切り餅、のしもちと色々で中に入れる具や、だし、みそ、しょうゆなどそれこそ数限りなくあるといってもよいくらいです。
それでも、新しい年を迎え、1年がつつがなく過ぎるようにと願う気持ちは、どこにいても同じだと思います。
お札を新しく頂き家の中を清め、おせちを頂いて新しい年を迎えることはありがたいことです。
結婚や出産など、新しい家族が増えて何よりだと思います。
今年も玄関に門松を飾って明るく元気に生きて行けるよう頑張りましょう!