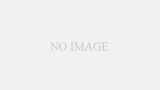お彼岸が近づくと、「暑さ、寒さも彼岸まで」というフレーズをよく耳にします。
気候的にも、暑さも和らいで少しづつ過ごしやすくなる頃ですね。
お彼岸には、家族揃ってお墓参りをする方も多いと思います。
ご先祖様や故人を偲び、感謝の心を込めて、
お墓や、お仏壇などにお供えをして先祖供養をしますよね!
お彼岸ってそもそもどんな意味があるのでしょうか?。
お彼岸は季節の節目にもなっていますが、
実際のところ、お彼岸の期間はどのようになっているのでしょうか?
ここでは、お彼岸の日はいつからいつまでなのか?」そして「春・秋の彼岸はいつ?」など、その期間についてまとめてみました。
お彼岸の時期と春分と秋分はいつ?
お彼岸には、春の彼岸と秋の彼岸と年に2回あります。
春の彼岸は、「春分の日(彼岸の中日)」を挟んで前後3日ずつの、
1週間を彼岸と呼んでいます。
秋の彼岸は、秋分の日を挟んで前後3日ずつの、1週間を彼岸と呼んでいます。
この春分と秋分の日は毎年、
・秋分は9月23日頃
となっています。
2022年(令和4年)春のお彼岸期間はいつからいつまで?
春のお彼岸は「春分の日」を中日として前後3日間。
この計7日間が「お彼岸」の期間とされています。
来年(2023年)の春分の日は3月21日(月・祝)なので、、
◆2022年(令和4年)春のお彼岸は3月18日(金)~3月24日(木)までの7日間↓
・3月18日(金)が 彼岸入り
・3月21日(月・祝)が 中日(春分の日)
・3月24日(木) が彼岸明け
2022年(令和4年)秋のお彼岸期間はいつからいつまで?
秋のお彼岸は「秋分の日」を中日として前後3日間。
この計7日間が「お彼岸」の期間とされています。
来年(2023年)の秋分の日は9月23日(金・祝)なので、
【2022年(令和4年)秋のお彼岸は9月20日(火)~9月26日(月)までの7日間】になります。
・9月20日(火)が 彼岸入り
・9月23日(金・祝)が 中日(秋分の日)
・9月26日(月)が 彼岸明け
まとめれば、
・春の彼岸:3月18日(金)~3月24日(木)
・秋の彼岸:9月20日(火)~9月26日(月)となります。
お墓参りをする場合は、この彼岸の期間中(1週間)の間に済ませるのが一般的です。
中でも中日(9月23日)に墓参りをするご家庭が多いですね。
余談ですが、春の彼岸を「彼岸」「春彼岸」というのに対して、
秋の彼岸は「秋彼岸」又は「のちの彼岸」と分けて呼ぶところもあるそうです。
お彼岸は何するの?
お彼岸にはご先祖様の霊を供養するために、お墓参りをする日なんですね。
そして墓にいくと、まず墓石や花筒などを洗い、
雑草を抜いてお墓の周りを綺麗に掃除をします。
その後にお花やお線香、お水をお供えし、
ご先祖様に手を合わせ、感謝の気持ちを伝えます。
墓参りが終われば、仏様が祀ってある家に赴き仏壇や仏具を綺麗にして、
定番のぼたもちや海苔巻きなど、そして故人が好きだったお菓子類などを供えます。
お供え物は地域によって風習が異なりますが、
基本は、ご先祖さまや故人が好んだ物をお供えするのば一番ですね。
お彼岸は春・秋となぜ年2回あるの?
お彼岸が年2回あるのは、実は太陽の動きに関係しています。
彼岸の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈むという不思議な現象が起こります。
この現象によってその日は昼と夜の長さが同じになるんですね。
この現象が、お彼岸の日である、
「春分の日」と「秋分の日」と年2回巡ってくるんですね。
その中心になる日が、「彼岸の中日」です。
太陽が真西に沈むこの春分と秋分は、太陽が浄土の方向を示すことから
彼岸と此岸がもっとも通じやすくなると考えられていました。
このため、彼岸の日にご先祖様の供養をすることで、
私たちも極楽浄土へ行くことができると考えられ、
春と秋の年2回のお彼岸にお墓参りをするようになったといわれています。
日本の寺院では、彼岸の期間中に彼岸会(ひがんえ)という法要を行い、
信者が詣で先祖のお墓参りをする風習が古くから行われていたようです。
ぼたもちとおはぎをお供えするのはなぜ?
春のお彼岸は、牡丹が咲く時期なので「ぼたもち」
秋のお彼岸は、萩の花が咲く時期なので「おはぎ」を食べます。
お彼岸にお供えするおはぎは定番中の定番ですが、
ここではなぜ、おはぎなのか?についてお話したいと思います。
おはぎの由来いろいろ?
お彼岸のお菓子として知られている「おはぎ」の名前の由来は諸説あります。
おはぎの名前の由来が一般的になっているのが、
秋に食べるのは秋に咲く「萩」の花から名付けられた
「おはぎ(お萩)」で、
春に食べるのは「おはぎ」ではなく、
春に咲く「牡丹」から名付けられた「ぼたもち(牡丹餅)」だという説。
季節の花の名前が付いているのは説得力がありますよね。
そのほか、もち米を主原料とするものが「ぼたもち」で、
うるち米を主原料とするものが「おはぎ」という説もあります。
もっと単純に伝わっているのが、
つぶあんが「おはぎ」で、こしあんが「ぼたもち」という説。
地域によっては、小豆あんを用いたものが「ぼたもち」で、
きな粉を用いたものが「おはぎ」だという説などいろいろあり、
今となっては由来は定かではありません。
現代では通年通して「おはぎ」と呼ばれることが多くなってきています。
おはぎとぼたもちはいつから食べられる?
2022年の場合だと、春分の日は3月21日になります。
そのため、2022年の春のお彼岸は3月18日(金)から3月24日(木)までの7日間です。
ちなみに2022年の秋のお彼岸は9月20日(火)から9月26日(月)までの7日間
一般的には春のお彼岸には「ぼたもち」が、秋のお彼岸には「おはぎ」が食べられます。
お彼岸とはなに?
お彼岸と言えば、即「墓参り」を思い浮かびますが、
意外とお彼岸について詳しい事を知っている人は少ないと思います。
ここでは、お彼岸の意味や由来などについてお話していきたいと思います。
「彼岸(ひがん)」は春と秋の年2回、各7日間、年14日間あります。
昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と「秋分の日」を中日とした前後3日ずつです。
本来の意味は、煩悩に苦しむ現世を意味する「此岸」に対して、
修行によって迷いを絶ち、「此岸」を渡りきった悟りの境地を意味する彼方の岸が「彼岸」ということです。
彼岸即ち「極楽浄土」は、西方の彼方にあると考えられており、
春分と秋分にはお日様が真東から昇り、真西に沈む事から、
その沈むお日様を礼拝し彼岸を想い、極楽浄土に生まれ変わることを願ったのが始まりとされます。
このため、彼岸の日にご先祖様の供養をすることで、
私たちも極楽浄土へ行くことができると考えられ、
お彼岸にお墓参りをするようになったといわれています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
お彼岸とは、「彼の岸」を意味し、
その語源は、サンスクリット語の漢訳語「到彼岸」からきています
お彼岸は昼と夜の長さが同じなる不思議な現象が起こる日でもあるんですね!
1年に2回ある春と秋のお彼岸は、太陽が沈む西に向かって手を合わせれば
極楽浄土に行けることで、深く日本の文化に浸透してきました。
また、春分・秋分のどちらの日も、
一年で最も気候の良い時期と思われるので、
ご先祖様に感謝の気持ちをあらわすには最適な時期ではないでしょうか。
今年の彼岸は今の気候が続くようでしたら、
暑いかもしれませんが、久しぶりのご先祖様とのご対面です。
お墓に、花やお供えをしてを感謝の気持ちを伝えましょう(*´∀`)