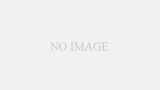お彼岸が近づくと、「暑さ、寒さも彼岸まで」というフレーズをよく耳にします。
気候的にも、暑さも和らいで少しづつ過ごしやすくなる頃ですね。
お彼岸には、家族揃ってお墓参りをする方も多いと思います。
ご先祖様や故人を偲び、感謝の心を込めてお墓参りをするものですが、
都合によってお彼岸にお墓参りにいけない場合があったりしますよね。
ここでは気になるお彼岸について、
・お彼岸に墓参りに行きたいのに、行けない・・。
・お彼岸過ぎのお墓参りは良くないのでダメ?午後の墓参りはダメなのか?
などお彼岸の墓参りについて、お彼岸の墓参りについて疑問に思うことと、
お墓参りや掃除道具、お供えものについてお伝えします。
お彼岸過ぎのお墓参りは良くない?
実家が遠方だったり、仕事などの都合で、
彼岸中にお墓参りが出来ない場合がありますよね。
行けなかった場合はご家庭に仏壇があれば、お仏壇にお線香を手向けて、
手を合わせるだけで大丈夫です。
また、お彼岸の期間中以外でも、帰省した際にお墓参りをしてもいいんです。
何よりも大事なことは、ご先祖様を敬い感謝する気持ちです。
この気持があれば、お墓参りはいつでもいいと思います。
言い換えれば、お墓参りは一年中いつでもOK!ということですね。
お彼岸のお墓参りは午前中?午後?
お彼岸と言えば、墓参りの時間を気にする人が多いと思います。
「午前中じゃないといけないの?」「午後からでもいいの?」
など、いざ墓参りをするとなると、時間の調整がつかず、
どうしたら良いのか、悩んだ経験がある方は多いと思います。
それには、まずお彼岸はどういうことなのか?
を理解していただければ、分かりやすいのではないでしょうか。
「お彼岸(ひがん)」は春と秋の年2回、
各7日間、年14日間あります。
昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と
「秋分の日」を中日とした前後3日ずつです。
お彼岸の本来の意味は、煩悩に苦しむ現世を意味する「此岸」に対して、
修行によって迷いを絶ち、「此岸」を渡りきった悟りの境地を、
意味する彼方の岸が「彼岸」ということです。
彼岸即ち「極楽浄土」とは、西方の彼方にあると考えられており、
春分と秋分には「お日様が真東から昇り、真西に沈む」事から、
その沈むお日様を礼拝し彼岸を想い、
極楽浄土に生まれ変わることを願ったのが始まりとされます。
このようにお彼岸は、春と秋、それぞれ7日間あり、
お墓参りは、沈むお日様を礼拝し彼岸を想い、
極楽浄土に生まれ変わることを願うことから始まったとされています。
しかし、お彼岸の墓参りの時間や日にちなど、
「いついかなければダメ!」といった決まりごとはありません。
地域により、家庭により、様々のようです。
しかし、昔の慣習として、何事も午前中に行うのが良いとされ、
墓参りも、午前中に行くのが慣習になったようです。
※お祝いを持っていくときと同じ気持ちでしょうか。
「仏さんが後から追っかけてくる」からだとか・・・。
まとめると、墓参りは午前中じゃなく、午後からでも問題なし、
「いつでもOK!」ということがわかりました。
午後から、お寺でのお墓参りをする場合、
お寺の閉まる間際に行くのはお寺に迷惑になりますので、
早い時間に済ませるようにしましょう。
お彼岸のお墓参りのお供え物は?

墓参りのお供え物に、特にこれをしなければいけないという、
決まりごとはなく、参られる方のお供え物は千差万別です。
お菓子にお酒、果物など、故人が好んだ物をお供えしてください。
お供え物は、お好きな物(お菓子、お酒、果物等)を、
すればいいと思いますがお参り後は、
お花以外は持ち帰った方がいいですね。
理由はいろいろあります。
その一つには、食べ物類は腐りますので、衛生上良くないのと、
野良犬や猫、そしてカラスなどにお墓を荒らされ汚くなることから、
お墓参りが終わり次第、持ち帰るのが慣習になったようです。
本来は、お供え物を持ち帰り、
ご先祖様と分け合って頂くのが一般的ですが、
お寺での墓参りの場合、持ち帰らずお寺へ、
ご供養として渡すところもあるようです。
その際は、予め包み紙などを用意しておくといいですね。
お供え物は、「共に供する」という意味合いもあり、
昔から、お供え物をお先祖様と分け合って頂くと、
供養になると言われています。
お彼岸のお墓参りのマナーは?

お墓参りに特別な作法などはありませんが、
一般的なお墓参りの仕方を覚えておけばいいでしょう。
ただ、宗派や、地域によっては、
お墓参りの仕方が変わるところもあるようです。
もし、わからない場合は、檀家の住職に尋ねるか、
もしくはm親族、親戚の方に尋ねて教えてもらうのが一番です。
ここでは、お墓参りをする時の必需品と、一般的な物をご紹介します。
◆お花
◆数珠
◆お線香
◆マッチ&ライター
◆お線香に火を付ける新聞紙等
◆お供え物(故人が好きだった物・一般的には、お菓子や果物)
◆お供え物を置く半紙
お鐘は、お勤め(読経など)をする時に使う道具なので、
お勤めをしない時は、あえて鳴らす必要がないそうです。
※実は管理人は、このことを知らずお墓まりをする時は、
当たり前の様に、お墓の前で鳴らしておりました。
両親のすることを見て育ってきたので、当たり前になっていたんですね。
<<お墓掃除の清掃道具>>
等の清掃道具が必要ですが、墓地、もしくはお寺によっては、
お墓の入り口に、清掃道具を保管する収納庫が用意されていて、
その収納庫の中に先程の清掃道具が、用意してあるところもあります。
これまで墓参りをする時に、用意する持ち物と、
お墓掃除の必要道具などについてご紹介しました。
次に、お墓参りをする時の手順など一通りの流れをお伝えします。
<<お墓の掃除>>
◆墓石を洗う(水をかけ、たわしで洗う)
◆墓石の家紋や文字などの細かい部分を、歯ブラシで汚れを落とす
◆水鉢や花立て、香立てを洗う(ゴミや葉っぱなど詰まりやすい物)
◆洗い終えたら、タオル等で拭き取る。
<<お供えをする>>
◆水鉢に新しいきれいな水をいれる
◆お供え物(お菓子など)を、半紙を敷いたその上に置く。
<<合掌礼拝を行う>>
◆お線香を手向ける
◆合掌礼拝をする。
※礼拝の時は、立ったままでするのではなく、
数珠を手にして額ずいて礼拝しましょう。
<<後処理>>
◆お供え物を持ち帰る◆お線香など火の気のあるものは、消化して帰る。
◆清掃道具を借りている場合、所定の位置に戻す。
※ゴミなどが出た場合、忘れずにきちんと持ち帰る。
お墓は、先祖や故人が眠っている大切な場所です。
形式的な墓参りをするより、ご先祖様や故人を敬う気持ちが大切です。
まとめ
お彼岸のお墓参りについて、お話しましたがいかがでしたでしょうか。
お墓参り時期や時間については、お彼岸に限らず、
故人を偲びご先祖様を敬う気持ちを忘れないことが大切ですね。
お参りの日時は自由、
大事なのは、いつも感謝の気持ちを忘れずに、
日々を大事に過ごすことじゃないでしょうか。
期間中じゃないといけない
その語源は、サンスクリット語の漢訳語「到彼岸」からきています
お彼岸は昼と夜の長さが同じなる不思議な現象が起こる日でもあるんですね!
1年に2回ある春と秋のお彼岸は、太陽が沈む西に向かって手を合わせれば
極楽浄土に行けることで、深く日本の文化に浸透してきました。
また、春分・秋分のどちらの日も、
一年で最も気候の良い時期と思われるので、
ご先祖様に感謝の気持ちをあらわすには最適な時期ではないでしょうか。
今年の彼岸は今の気候が続くようでしたら、
暑いかもしれませんが、久しぶりのご先祖様とのご対面です。
お墓に、花やお供えをしてを感謝の気持ちを伝えましょう(*´∀`)