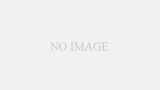お彼岸は、1年に2回やってきます。
春のお彼岸、秋のお彼岸と、私たちの先祖供養をする大切な日です。墓参りの習慣として、お盆に墓参りをしますが、お彼岸のお墓参りはいつするのでしょうか?
お彼岸の墓参りの期間は、お彼岸には「彼岸の入・彼岸の中日・彼岸の明け」の言葉にあるように、一般的に、この期間に墓参りをすればいいということになっています。
ちなみに2023年の秋の彼岸は下記のようになっています。
お彼岸と言えば、即「墓参り」を思い浮かびますが、意外とお彼岸について詳しい事を知っている人は少ないと思います。
この記事では、当たり前になっているお彼岸の墓参りについて、
・意味と期間は?年2回墓参りをする理由
について分かりやすく解説します。
また、お彼岸は毎年の慣習ですが、年によってお彼岸の日が変わります。2023年の秋のお彼岸はいつなのか?ご先祖様の供養をしっかりするために、お彼岸の期間を覚えておきましょう!
お彼岸の墓参りの参考にして頂ければ嬉しいです♪
お彼岸の期間はいつからいつまで?
お彼岸には「彼岸の入、彼岸の中日、彼岸の明け」といわれ、一般的には、この期間に墓参りをすればいいということになっています。
秋の彼岸は、秋分の日を挟んで前後3日ずつの1週間を彼岸と呼んでいます。
ちなみに2023年の秋の彼岸は、
となります。
お墓参りをする場合は、この彼岸の期間中(1週間)の間に済ませるのが一般的です。
中でも中日(秋の場合:9月23日)にスケジュールを合わせて墓参りをするご家庭が多いですね。
また、春の彼岸を「彼岸」「春彼岸」というのに対して、秋の彼岸は「秋彼岸」又は「のちの彼岸」と分けて呼ぶところもあります。

秋の彼岸は、ご存知のように「秋分の日(彼岸の中日)」を挟んで、前後3日ずつの1週間を彼岸と呼んでいます。
お墓参りは基本的に、都合の良い時にすればいいと思いますが、
お彼岸の墓参りは、彼岸の期間中で、天候に恵まれた穏やかな日を選び、家族で参るようにしましょう。
※ちなみに我が家では墓参りはできるだけ午前中にお参りするようにしていますが、年によっては仕事の都合上夕方にお参りする場合もあります!
お彼岸の意味は?
彼岸の意味を解っている人はかなり博識の方だと思いますが、いかがでしょうか?
高齢者の人は知っている人は圧倒的に多いと思います。半面、最近の若い世代の人は殆ど知らないと思います。
本来の意味は、煩悩に苦しむ現世を意味する「此岸」に対して、修行によって迷いを絶ち、「此岸」を渡りきった悟りの境地を意味する彼方の岸が「彼岸」だったといわれています。
彼岸即ち「極楽浄土」とは、西方の彼方にあると考えられています。
春分と秋分には太陽が真東から昇り、真西に沈む事から、その沈む太陽を礼拝し彼岸を想い、極楽浄土に生まれ変わることを願ったのが始まりとされます。
この考え方が、中国から日本に伝わり、日本独自の習慣や文化、そして仏教と結びつき、祖先を祀り、墓参り等が行われる仏事へと変化して行ったようです。

余談ですが、西方浄土をお守りする仏様を「阿弥陀如来」といい、日本では「阿弥陀さま」と呼んで親しまれています。
春彼岸と秋彼岸の違いは?
お彼岸は、ご存知のように「春分の日(彼岸の中日)」と、「秋分の日」があり、前後3日ずつの1週間をお彼岸と呼んでいます。
春彼岸と秋彼岸では何か違いがあるのでしょうか。
結論から言えば、春彼岸と秋彼岸にほとんど違いはありません。
敢えて違いを言えば、お供えする「あんころ餅」の呼び名が変わるくらいですね。
「あんころ餅」という呼び方は、春彼岸では「ぼたもち」、秋彼岸では「おはぎ」という呼び名になります。
春は牡丹が咲くので「牡丹餅」、秋には萩の花が咲くので「お萩」なんだそうです。
地方によっては、秋に取れた小豆は皮が固くなるので、「ぼたもち」はこしあんで作ることもあるようです。
しかし、お餅の呼び方が変わってもすることは同じです。春でも秋でも変わらずにご先祖様を大切に供養しましょう。
お墓参りでは何をする?
お彼岸は先祖のお墓参りすることですが、その前に下記に挙げた流れでお墓掃除をする必要があります。
具体的にお墓参りの順番がありますので紹介します。
の順で行います。
ここでは、順に沿ってお墓参りで行う事を紹介していきます。
服装は普段着でOK!
お彼岸の墓参りは、服装は普段着で問題はありません。ただ、室内で着るような軽装着、またはお洒落な服装は避けるようにした方がいいですね。
もしご親族等が集まってお墓参り等をする時は、もう少し改まった服装がいいですね。黒や灰色など地味な服装で、少しフォーマルな服を着て見ましょう。
お墓を掃除をしてきれいにする
お墓の掃除について、順を追って説明します。
準備する道具は以下の通りです。
・たわし
・布
・歯ブラシ
・バケツ
・軍手、花ばさみなど(雑草を手入れする道具)
1.ごみ袋を用意し、お墓の周りを掃き掃除、そして雑草を取ります。
(その後、除草剤を撒くことがあります)
2.墓石は水をかけながら、布&たわしやでこすり奇麗にします。
ご先祖様の名前が刻んである部分は、歯ブラシで掃除しましょう!
そして、汚れた水鉢や花立の水も取り替えて綺麗に洗いましょう。
最後に乾いた白布で水をふき取ります。
花、おはぎ等のお供え物をする
お墓の掃除が終了すれば、墓全体に水を打ってからお供えをしましょう。
基本的なお供え物は以下の通りです。
・ロウソク
・お花
・浄水
・リン
・故人が好きだった食べ物など
この他、春彼岸の場合は「ぼたもち」そして秋彼岸の場合は「おはぎ」をお供えしましょう。食べ物や飲み物などは半紙を二つに折ったものを敷いて、その上に置きます。
合掌して故人の冥福を祈る。(合掌する時は、必ずしゃがんが状態で行いましょう)
お供えをしたら、数珠を持って合掌します・・・(地域によって、般若心経を拝む所があります)
お供えしたものは全部持ち帰る
お墓参りが終われば、お供えに持ってきたもの全部持って帰ります。
お供えしたままだと、突然の雨、風で飛ばされた時に、隣の墓地に迷惑になる場合があります。
特に食べ物は、鳥や動物が食べに来て、お墓を汚す場合があるので注意しましょう。
なのでお供えは、その場で食べてしまっても大丈夫です。
また、お花も花粉などで墓石が汚れてしまうことがあります。
霊園では場合によってお花が古くなったり、痛んだりすると下げてくれたりします。
基本的には持ち帰った方がいいですね。
まずは、お墓参りの場に物を残さないようにする事が大切です。
お寺の合同法要のお布施の相場は?
お彼岸には多くのお寺で合同法要が催されます。
合同法要に参加する時は、お布施を用意するのが一般的です。
金額の相場は「3千円~1万円」と言われています。(コロナの影響で相場が変動しているかも?)
地域によって違いがあるので、お寺さんに直接聞くのがいいですね。
また、親戚や、隣保の人に聞いて見るのも一つの方法です。
包装は白無地の封筒で構いません。
表書きは「御布施」が良く書かれます。
合同法要は必ずしも参加しないといけないものではありません。
なので、お墓参りだけで問題ありません。
お彼岸の墓参りの時期と時間は?
お彼岸のお墓参りの時期と時間ですが、いつ行けばいいのでしょうか?
◆一般的には前述の通り、春分の日・秋分の日の前後に行くのが通例です。
◆墓参りの時間帯としては、午前中が良いでしょう。
理由は、ご先祖様が他の用事よりも優先されるため、一番に行くという考え方が根底にあるんですって。
いろいろと理由を作るものですね。
しかしこのような理由がない場合でも、墓掃除や雑草の手入れなど意外と時間を取られます。
ゆっくりと丁寧に墓掃除をするためにも、出来れば午前中に行きましょう。
暗くなると掃除し難いばかりか、階段など、段差のある墓地は足元が危いので用心しましょう。
遅くても、4時頃までの日の明るいうちにお参りを済ませる事がベストです。
また、お彼岸の期間だけ、開園時間が変更になっている霊園もあるので、
事前に日程を確認するようにしましょう。
お彼岸の時期は駐車場や車も混雑する可能性があるので、
霊園の管理事務所にピークの時間帯も聞いておくとスムーズにお参りができます。
お彼岸は春と秋の年2回あるのは何故?
お彼岸が年2回ある理由は、太陽の動きに関係していたんですね。
宇宙の動きに合わせて、お墓参りをする習慣ができるなんて凄い発想ですよね。
日本の寺院では、彼岸の期間中に彼岸会(ひがんえ)という法要を行い、
信者が詣で先祖のお墓参りをする風習が古くから行われていたのです。
お彼岸に墓参りでは何をするの?
前述の通り、彼岸とは、字のごとく「彼方の岸」のことで、
これと真逆の意味を持つ言葉が「此岸」なんですね。
仏教では、厳しい修業をして悟りを開いた者だけが住む「悟りの世界=極楽」。
それに対して「煩悩に満ち溢れた世界=現世」
これを此方の世界いわゆる「此岸」と呼んでいます。
今よりはるか昔、お釈迦様が古代インドにて、この汚れきった世の人々を、
救う何かよい手立てはないかと出家の末、仏教という道が開かれました。
仏教では、修業し悟りを得た者たちだけが住む「彼岸」は西方浄土にあると考えられていて、
1年のうちで一番太陽が真西に沈むこの日を、「彼岸」と呼びます。
この期間中に仏様のご供養を行う事で極楽浄土へ旅立ことができる、
という考えから先祖供養が始まり、彼岸のお墓参りが私たちの慣習となりました。
余談ですが、墓参りには1人で行くのは、引っ張らるから駄目とか、
また、首から枯れて落ちる花は駄目、そして墓参りは必ず午前中に、
午後から行くと、仏さんが追いかけてくるから駄目。
最後に、ついで参り、ついで拝みは駄目と言われてきたのを記憶しています。
迷信だと思いますが、なんとなく妙に納得してしますよね!
墓参りの際の参考になれば嬉しいです。
まとめ
日々忙しく働いていると、ついご先祖さまの存在を忘れがちになることが有ると思います。
お盆、彼岸に墓参りで供養をするのも大切な行事ですが、
その墓参りが行事だけで終わらないようにしたいものです。
ただ、形式にこだわった供養だけではご先祖さまも悲しまれます。
先祖供養は普段から、私たちの変わらない先祖様を慕い敬う心を伴うことが大切です。
ご先祖様の想いは常に変わることなく、絶えず子孫の繁栄と安寧を願っておられます。
多くの人々がお彼岸やお盆だけでなく、朝晩仏壇の前で、
先祖に手を合わせる習慣をつける事が、一番の供養かと思います。
ちなみに、私の朝の日課は、
仏壇にお水とお線香を供え、開経に始まり般若心経を5回唱えて終わります。
その間、20分足らずですが、気持ちが落ち着きます(*´∀`)