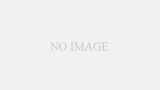お正月が終わって仕事始め。
まだ、お正月気分がなんとなく抜けきらないけれど、
いつまでもそうはいきませんね。
気持ちも新たに新しい年に突入です。
ところで、年末に飾ったしめ縄やしめ飾りはいつ外すでいいのか?
はずした後はどうしたらいいのか、迷ってしまいますね。
お正月に飾ったものだし、いい加減にできないし、
どうしていいのか分からず処理に困った人は多いのではないでしょうか。
では、ここで一緒に「しめ縄やしめ飾りの外す時期」について考えてみましょう。
しめ縄・しめ飾りはいつ外すの?
お正月にお世話になったしめ縄やしめ飾り。
いつまで飾っておいていいのでしょうか。
一般に、しめ縄やしめ飾りは「松の内まで」といわれています。
「松の内」とは、正月飾りの一種である松飾りを飾っておく期間の事を言います。
松飾りとは門松を指しますが、
門松は歳神様が道に迷う事なく家に来るための目印とも、
家に歳神様の滞在を示す印とも言われています。
この門松を飾っておく期間の事を「松の内」と言います。
松の内は地域によっても違うのでまた、後で詳しく書きます。
参考までに、しめ縄や門松などのお正月飾りの飾り付けは、
現在はクリスマスの後から30日までに済ますというのが主流になっています。
クリスマスの後、26日~28日頃までに飾り付けを行うことが多いようですね。
ただ、気を付けたいのが、29日は二重苦(苦が付く)、
31日は一夜飾り(一晩だけの飾り付けで神様に失礼にあたる)といわれ、
正月飾りには良い日ではないとされています。
遅くなってしまった場合は、30日に飾るのが良いでしょう。
クリスマスが終わったらあっという間にお正月の準備。
一年が経つのは本当に早いです。
松の内とは何?
松の内(まつのうち)について整理しておきましょう。
前述したように松の内とは門松などの正月飾りを飾っておく期間のことをいいます。
松の内の始まりは元旦です。
松の内の終わりは関西と関東で違いがあります。
・関西では、1月15日まで、
・関東では、1月7日まで、
となっており、地域によって差があります。
しめ縄の処分方法と時期は?
しめ縄をはじめとした正月飾りは、どんど焼きと言われる、
正月に行われる火祭りで燃やして片付ける地域が多いですね。
どんど焼きは小正月の1月15日に行われ、これは正月にお家に来て頂いていた歳神様に、
焚き上げた煙と共に天に帰ってもらう、と言った意味があるのです。
どんど焼きでしめ縄や正月飾りなどを焼くことは、
飾ってあるものに憑いた歳神様をお送りし、無病息災を祈る行事なのです。
大抵は、どこの神社でもどんど焼きの行事が行われているかと思います。
私のうちの近所の神社でも毎年必ず行われています。
しめ縄の処分にはお金もかからないので、
開催の有無や場所が分からなければ、一度神社に問い合わせてみてください。
私も毎年、必ず、持っていっています。
都合がつかず1月15に行くことができなかった、
あるいは近くに神社がない場合はどうするか?
実は15日ではなくとも神社に納めることはできます。
だいたいの神社では受け取ってもらえますが、事前に確認するのが大事です。
しめ縄やしめ飾りは地域によって違うの?
しめ縄やしめ飾りを出しておくのは、「松の内」までです。
そして、松の内の期間は、住む地方によって2つのパターンがあることに気を付けましょう。
・関東は1月7日まで、
・関西は1月15日まで、
と地方で違いがあります。
このように松の内が地域によって違うのは、以下のような理由があるからとされています。
元々、松の内は小正月である15日とされていました。
そして、歳神様にお供えをしていた鏡餅を下げて食べる鏡日開きを、
20日に行っていたのですが、
時の将軍、徳川家光が4月20日に亡くなった事により、
20日という日を忌み嫌うようになった徳川幕府が、
20日よりも前の11日に鏡開きを行う事にしたのです。
これにより関東地方を中心とした地域では、松の内も7日と変更されたのです。
また振袖火事と呼ばれる明歴3年の正月18日から28日に起こった大火を教訓に、
幕府から7日を以て飾り納めをするという通達があったため、とも言われています。
このように関東では7日までを松の内とする流れが生まれたのに対し、
幕府の影響をそれほど受けなかった、
関西地方では、今も元からの15日を松の内とする地域が多いようです。
しめ縄に限らずお正月の飾りは松の内の期間が終わったら処分しましょう。
まとめ
しめ縄、しめ飾りについてお話しましたが、
いかがだったでしょうか?
さて、みなさんはどのようなお正月を過ごされましたか。
お正月が済んだら、お正月で飾ったものにも感謝を込めて処分しましょう。
今年一年があなたにとって良い年でありますように。