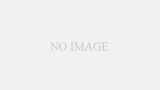「暑さ、寒さも彼岸まで」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
彼岸が近づいてくると、両親、祖父などからこのフレーズを聞かされて育ってきた方は多いのではないでしょうか?
お彼岸が近づく度にこのフレーズが思い起こされます(*´∀`)
お彼岸は、お墓参りに行ってご先祖様を供養するとは分かっていても、
恥ずかしい話、彼岸の意味や、何故墓参りをするのか、何故おはぎなどをたべるのか?
など、その理由を知らないでお彼岸を過ごしてきました。
あなたもそうじゃないでしょうか?
私たちは、普段何気なく生活を送っていると、
いざ、これってどういう意味って聞かれても応えることが出来ないことが多いですね。
今回は、この彼岸の意味や由来、墓参りやおはぎを食べる理由などについて触れて行きたいと思います。
お彼岸の意味とは?
「彼岸(ひがん)」は春と秋の年2回、各7日間、年14日間あります。
昼と夜の長さが同じになる「春分の日」と「秋分の日」を中日とした前後3日ずつです。
本来の意味は、煩悩に苦しむ現世を意味する「此岸」に対して、
修行によって迷いを絶ち、「此岸」を渡りきった悟りの境地を意味する彼方の岸が「彼岸」ということです。
彼岸即ち「極楽浄土」とは、西方の彼方にあると考えられており、
春分と秋分にはお日様が真東から昇り、真西に沈む事から、
その沈むお日様を礼拝し彼岸を想い、極楽浄土に生まれ変わることを願ったのが始まりとされます。
この考え方が、中国から日本に伝わり、日本独自の習慣や文化、そして仏教と結びつき、祖先を祀り、墓参り等が行われる仏事へと変化して行ったようです。
そのため日本の寺院では、彼岸の期間中に彼岸会(ひがんえ)という法要を行い、
信者が詣で先祖のお墓参りをする風習が古くから行われてきています。
余談ですが、西方浄土をお守りする仏様を「阿弥陀如来」といい、
日本では「阿弥陀さま」と呼んで親しまれています。
暑さ寒さも彼岸までとは本当?
冒頭にも書きましたが、「暑さ寒さも彼岸まで」というフレーズは、
耳にタコができるほど聞かされてきましたが、本当なのでしょうか?
彼岸は、昼と夜の長さはほぼ同じになりますが、
春分と秋分の気温が同じにはなりません。
※時間は同じでも、季節が違うので気温が違うということですね!
年によりますが、春分の日の平均気温は10℃前後、秋分の日は20℃前後になります。
春分の日と、秋分の日とでは随分と温度差があるのが分かりますよね。
これを見ると、春と秋とでは、温度差が激しい分、
寒さ暑さが和らいでいるのが分かりますね
前述の内容に基づけば、
「暑さも寒さも彼岸まで」とは、「冬の寒さは春分の頃までで、その後はだんだんと暖かくなる」
「夏の暑さは秋分の頃まででその後は過ごしやすい気候になる」という意味ですね。
お彼岸の由来は日本独自の文化?
それぞれ国民の祝日を定める法律で見てみると、次のように謳ってあります。
春分の日:自然をたたえ、生物をいつくしむ。
秋分の日:先祖をうやまい、亡くなった人を偲ぶ。
春分・秋分の日は、農耕という視点から見ると、
・草木が芽吹き豊作を願う春と、
・農作物が収穫されて、自然の恵みに感謝する秋になります。
今でこそ、仏教的な行事になっているお彼岸ですが、
実は、お彼岸にお墓参りをする文化は日本独自のもので、他の仏教国では行われないそうです。
春のお彼岸特集① ~お彼岸ってなぁに?~
元々農耕民族であった日本人は、仏教が伝わる前から、
自然の恵みに感謝し、先祖供養する習慣がありました。
この日本古来の風習が仏教と結びつき、春分・秋分の日を中心に、
先祖供養をするようになったといわれています。
お彼岸にお墓参りをする文化には、日本独自の価値観が大きく息づいているように感じます。
お彼岸になると、おはぎやぼた餅を食べる習慣がありますが、
なぜ、いつからこのような習慣が定着したのでしょうか?
その由来などを紐解いてみました。
お彼岸におはぎを食べる訳とは?
神話で少し堅苦しい話になりますが、
日本神話では、天照皇大神(あまてらすおおかみ)が高天原(天の神の世界)の稲穂を下さった事になっています。
そしてその天の稲穂(米)を人間が育て聖なる食べ物として、有難く、感謝して頂戴しました。
米や稲には神霊が宿り、それを頂くことで我々は神の力を賜ることができると言われています。
米は単なる食料ではなく、神々しき魂のこもった霊的な存在でもあるんですね。
それを神前に献じ、神話からの神々や先祖や皇室や命や国土や魂や天地宇宙万物に
報恩感謝の誠を捧げます。
稲(米)を授けた天照皇大神は太陽神ですので、
太陽に関係する時期に、米に関する行事を行うようになりました。
◆太陽が中間の頃の先祖崇拝=彼岸=ぼたもち・おはぎなど
◆太陽が弱い頃の先祖崇拝= 正月=もちなど
◆太陽が強い頃の先祖崇拝= お盆=だんごなど
米や小豆などは、縄文遺跡からも発掘されているので、
古代から日本人とは密接な関係にあったということですね。
これらは仏教伝来以前の日本固有の文化とし栄えたので、
外国の仏教徒は、おはぎやぼたもちを彼岸に供えたりはしません。
以上、ちょっと小難しい神話話しが入りましたが、
前述のように、お彼岸におはぎやぼた餅を食べる習慣に繋がっていったようです。
古代から米は日本にとって大切な食料だったのがよくわかりますね。
おはぎの名前の由来は?
お彼岸のお菓子として知られている「おはぎ」の名前の由来は諸説あります。
そのうち有名なものは、秋に食べるのは秋に咲く「萩」の花から名付けられた「おはぎ(御萩)」で、
春に食べるのは「おはぎ」ではなくこの時期に咲く「牡丹」から名付けられた「ぼたもち(牡丹餅)」だという説です。
季節の花の名前が付いているのは説得力がありますよね。
そのほか、もち米を主原料とするものが「ぼたもち」で、
うるち米を主原料とするものが「おはぎ」という説もあります。
もっと単純に伝わっているのが、
つぶあんが「おはぎ」で、こしあんが「ぼたもち」という説。
地域によっては、小豆あんを用いたものが「ぼたもち」で、
きな粉を用いたものが「おはぎ」だという説などいろいろあり、
今となっては由来は定かではありません。現代では通年通して「おはぎ」と呼ばれることが多くなってきています。
管理人も未だに、恥ずかしい話ですが、
おはぎとぼた餅の違いがよく理解できていないところがあります(*´∀`)
まとめ
遠距離でお墓が遠くてなかなかお墓参りをする暇がないと言う方も、
この彼岸の時期こそ、西の方向に手を合わせてみてはいかがでしょうか。
また、先祖の供養だけでなく、五穀豊穣や無病息災を願い、
おはぎを頂く日本の伝統的な食習慣も子どもたちに伝えられたらいいですね。
管理人も甘党で甘いものに目がありません。
夏場は少し控えめですが、秋の彼岸が近づくと無性に甘いものが食べたくなります。
おはぎ恋しさに近くの道の駅の売店まで、購入に出かけます。
また、性格がせこいので閉店間際を狙っていきます。17:00以降になると割引になりますので(*´∀`)